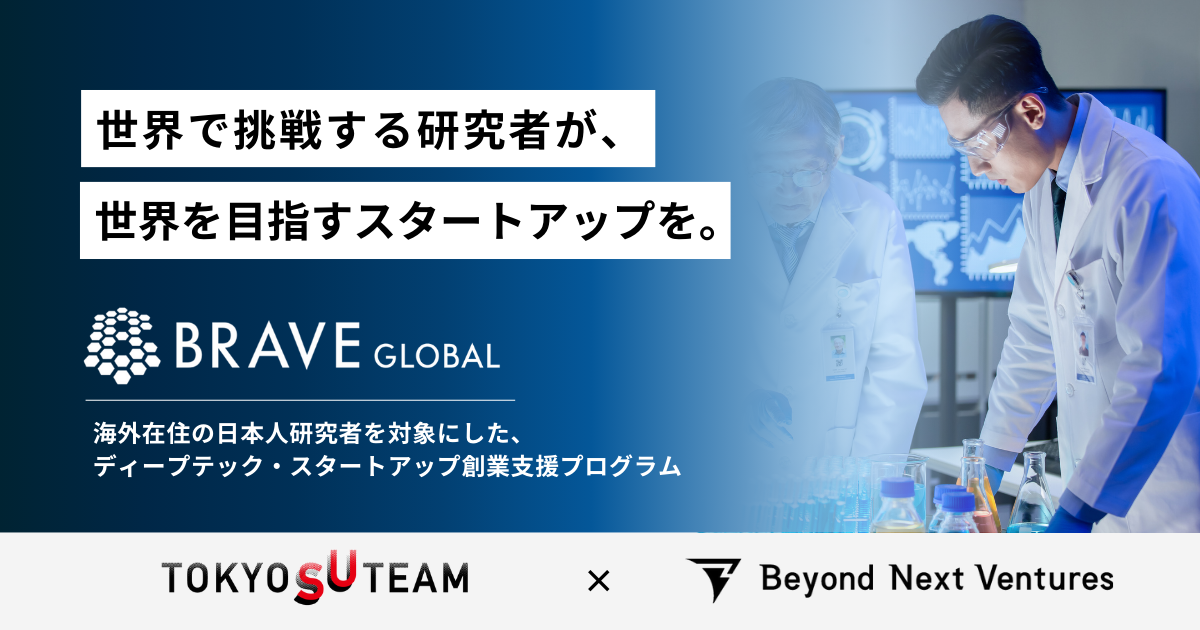有馬:シード期のディープテック・スタートアップに投資をするベンチャーキャピタルのBeyond Next Venturesで、アグリ・フードテック分野の投資を手掛ける有馬です。
今回は、ニューヨークで「イチゴの植物工場」を運営するOishii FarmのCEO古賀大貴氏に、起業ストーリーや事業戦略について伺いました。NYで創業し、2024年2月には200億円の資金調達を発表した同社。なぜ「イチゴの植物工場」を「ニューヨーク」で始めたのか?また、Day1から海外で創業してどんな苦労を乗り越えてきたのか?世界を目指して起業したい方にぜひお読みいただきたい内容です。
【Podcastでも配信中です!】

プロフィール

Oishii Farm 共同創業者 兼 CEO
古賀 大貴
1986年東京生まれ。少年時代を欧米で過ごし、2009年に慶應義塾大学を卒業。コンサルティングファームを経て、UC バークレーでMBA を取得。在学中の2016 年に「Oishii Farm」を設立し、日本人として初めて、同大学最大のアクセラレーターであるLAUNCH で優勝。2017年から米ニューヨーク近郊に植物工場を構え、日本品種の高品質ないちご、トマトを展開する。日本発の技術を基盤に、農業の課題解決に挑戦している。

Beyond Next Ventures株式会社 パートナー
有馬 暁澄
2017年4月丸紅入社。穀物本部にて生産から販売までのアグリ全般に携わる。また、アグリテック領域のスタートアップ投資チームを立ち上げる。2019年に当社に参画し、アグリ・フードテック領域のスタートアップへの出資・伴走支援に従事。2022年にパートナーに就任。農林水産省や大企業と連携し、産学官連携プロジェクト(農林水産省「知」の集積プログラム、「フードテック研究会/ゲノム編集WT」代表、スタートアップ総合支援事業「AgriFood SBIR」PMなど)にも取り組む。目標はアグリ・フード領域のGAFAを生み出すこと。慶應義塾大学理工学部生命情報学科卒業。
目次
世界初、植物工場での果菜類の量産技術を確立
有馬:まず最初に、ぜひOishii Farmの植物工場について教えていただけますか。
古賀:私たちはDay1から米国のニューヨークで植物工場を作り、農作物を栽培しています。今はイチゴの栽培にフォーカスをしており、2022年6月からは、米国の大手高級スーパー「ホールフーズ」にて1パック約10ドルで販売を開始しました。米国のイチゴの平均単価は5ドル以下なので、高級イチゴとして認識されています。

植物工場は、一切太陽光が入らない完全閉鎖型の室内でLEDやエアコンを使って農作物を育てる技術で、いまや農業のサステナビリティなソリューションとして世界中で注目を集めています。実際に私たちの植物工場では、従来の手作業による栽培方法に比べ、エネルギー使用量約60%・水使用量約40%を削減することができました。
これまで植物工場で農作物を育てるとなれば、レタスなどの葉物野菜が一般的でした。なぜなら、イチゴやトマトなどは「受粉」が必要で、工場の中でハチを飛ばす必要があり、その技術的難易度は非常に高いからです。しかし私たちは、この課題を克服し、植物工場内での精度の高いハチ受粉の技術を確立し、これまで植物工場では作ることのできなかった果菜類の量産に成功しました。
有馬:たしかに、世界には植物工場が数多く存在しますが、イチゴを栽培できる植物工場はかなり限られるので、そこが一番のユニークポイントですよね。
「日本の農業は世界で勝てる」MBA卒業翌日に起業
有馬:もともと古賀さんはコンサルファームにいらして、その中で植物工場を選んだ理由はなんだったのでしょうか?

古賀:私は理系でもないし手に職があるわけでもなかったですが、自分で何かやりたいと思っていました。新卒で就職したコンサルファームでの仕事を通じていろいろな産業を見てきた中で、「日本が世界で戦える産業だ」と強く感じたのが「農業」だったのです。
一見、農業は斜陽産業と思われがちですが、実は日本の農作物の品質は世界トップクラスで、大きなポテンシャルを持っています。また、10年以上も早くから世界に先駆けて植物工場は流行していますし、施設園芸の技術レベルも米国と比較にならないほど優れています。結果的に国内では植物工場の市場は確立できなかったものの、「やり方次第で世界をリードできる」と確信しました。
そんな中、私はMBAを取得するためにUCバークレーに留学をしました。今考えると本当にタイミングが良かったなと思うのですが、当時は世界的にサステナビリティが大きなテーマになっており、米国でも日本より10年遅れで植物工場が流行り始めていた時期で、大きなビジネスチャンスだと感じた私は、卒業した翌日に起業しました。
有馬:タイミングがよかったんですね。
古賀:はい、完全にタイミングと運とすべてが重なったと感じています。
Day1から海外での起業は試練の連続
有馬:米国でゼロから起業して一番大変だったことは何ですか?
古賀:海外での起業は本当に苦労の連続でした。今でこそニューヨーク在住7年目ですが、起業当時は現地にネットワークもありません。当然現地ではマイノリティですし、信用力もなく、第二言語で戦わなければならない…など、「不」しかない状態でした(笑)。丸裸で戦わされている感覚でしたね。
有馬:米国ではコミュニティに属することが一つのカギだったりしますか?
古賀:それはその通りで、今でこそ少しづつ変化の兆しはありますが、当時の植物工場業界トップ5の企業は、CEO全員がアイビーリーグやスタンフォード大学などトップ校出身の白人男性で、知り合いの投資家から資金を調達していました。それも、「自分の奥さんの弟が投資家で…」とかそういう世界です。
そのようなコミュニティが成立している世界で自分は移民として見られるため、どれだけ自分のビジネスに自信があっても、話すら聞いてもらえないことも少なくなかったですね。
有馬:そのようなビハインドな状況を打開するために、何が最も効果的でしたか?
古賀:現地のパートナー(共同創業者)の存在は必須でした。特に私たちは日本で圧倒的な実績を携えたうえでの米国進出ではなく、本当にゼロから米国で事業を立ち上げたので、より一層重要でした。
一緒に自分と戦ってくれるパートナーがいることで精神的な支えにもなりますし、そこから現地のネットワークも手に入るため、事業の進み方も大きく変わります。米国で起業する人は、まずは現地のパートナーを探すことをおすすめします。
有馬:プロダクトを売るうえでのビジネス的なハードルはありましたか?

古賀:その土地の感覚値がないことには苦労しました。一般的な米国での生活様式をイメージできないため、いくらが妥当なのか、ネーミングセンスはどうか、など沢山悩みました。
たとえば、社名の「Oishii」だって、日本なら微妙だと思われそうですが、米国ではどんなイメージが持たれるのか、そもそも発音しやすいのか、見当もつかないのです。実は私はこの社名に最初は懐疑的でしたが、共同創業者のブレンダンが「このイントネーションは米国でウケるよ。“ii”で終わる言葉は(“Kawaii”と似ていて)日本らしい」と教えてくれました。さらに、「おいしい」というワードは、「日本に行ったことがある人なら知っている可能性が高い言葉なので、受け入れてもらいやすいだろう」と言われ、採用することにしたのです。そういった細かいこと含めて、現地の文化や国民性を深く理解しているパートナーの有無によって事業の進み具合は大きく変わることを実感しました。
有馬:面白いですね。あと、御社はポップアップストアをよく出されていて、現地の人たちの反応を直接見ていましたよね。
古賀:はい、肌感覚を早く掴みたかったので。
有馬:やはり食文化は全く違いますか?
古賀:全然違います。例えば、日本では「千疋屋」で高級なフルーツを購入できますよね。しかし米国では、野菜や果物の「高級ライン」が存在しないんです。5ドルを超えるイチゴは売られていません。つまり、私たちのイチゴは販売当初は50ドルだったので、そもそも存在しない市場だったんです。現在はコストダウンに成功し10ドルで販売していますが、それでも現地では市場がないほどの高級カテゴリーです。
創業メンバーは全員リファラル
有馬:共同創業者であるブレンダン氏との出会いについて教えてください。
古賀:UCバークレー在学中に起業を決意した時から、米国で事業を立ち上げるなら現地のパートナーが必要だと考えていました。そこで友人から紹介されたのが、後の共同創業者となるブレンダンでした。ブレンダンはシリアルアントレプレナーで、かつ、海軍時代に日本に住んでいた経験をもっており、日本への理解もありました。
私たちは意気投合して、MBA在学中に二人で起業しました。私が主に資金調達を担当し、ブレンダンは主に植物工場の立ち上げに集中しました。
有馬:そのほかの経営メンバーはどのように見つけたのですか?
古賀:すごくラッキーだったのは、私たちの事業が「サステナビリティ」や「人類の食の未来」といったテーマだったため、共感を得やすかったというのはあると思います。その中で、「私たちは農業界のテスラになるんだ」という30年後の壮大なビジョンに共鳴してくれた数人が、まず入社してくれました。
この初期に入ってくれたメンバーがとても素晴らしくて、彼らが周りにいる人たちを連れてきてくれて、どんどんチームが拡大していきました。
有馬:リファラルが多いんですね。
古賀:ほぼリファラルですね。今従業員数は200名ほどで、マネジメント層は20数名いるのですが8割以上がリファラルです。ようやく最近一般的な採用活動を始めました。
有馬:日本のスタートアップが海外に行くときに一番最初に困るのが人材面だと思うので、リファラルは強いんだなと思いました。
古賀:最初の数人に本当に良い人を仲間にすることができれば、その人たちは優秀なネットワークを持っていることが多いので、芋づる式に良い人に出会えると思います。
イチゴの決め手は、味・技術・ブランドの差別化のしやすさ
有馬:イチゴに決めたのはいつ頃ですか?起業された当時は、植物工場と言えば葉物系しかなかった時代だと思うのですが。

古賀:非常に大きな転機がMBAコース一年目の夏休みにありました。当時、シリコンバレーの投資家による植物工場への投資が増えていたのですが、私にデューデリジェンス(DD)の依頼が数件ありました。コンサルファームで日本の植物工場を担当していた経験を買われたようです。
DDを通じて投資家視点で植物工場を分析すると、どの企業も「レタスしか」育てていないことに気づきました。なぜなら育てるのが簡単で、資金調達をして研究開発をすれば数年後に黒字化できる見込みがあったからです。
しかしそれは10年前に日本が辿った道とまったく同じで、5年も経てば儲からない商売になってしまうだろうというのが分かってきました。
逆を言えば、30年や40年という長期スパンで考えたときに、植物工場の技術で5年後に儲かるビジネスモデルを作ることができれば、競合がいない市場なので勝つことができると考えました。
有馬:なるほど、その時から逆算で考えていたのですね。
古賀:はい。その中でイチゴに決めた理由は3つあります。味、技術、ブランド の3つの観点すべてにおいて、「どれだけ差別化しやすいか」が重要であると考えました。
イチゴは味に差が出やすく、良い味を出せれば高い値段でも売れるだろうと考えました。技術については、誰も成功したことのないハチによる受粉技術を早期に確立できれば競争優位性につながるだろうと。そして、ブランドについては、いつか技術が陳腐化したとしても、「Oishii Farmが一番美味しい」という先入観が築かれると、そう簡単に競合が割り込めません。新しい品種が「あまおう」の牙城を崩すのに苦戦しているのと同じ構図です。
有馬:ブランド力でモノを買うというのは、僕も多くのフードテックスタートアップに投資をしていて、すごく共感するところですね。
マーケットドリブンでゼロから技術を創り上げる
有馬:古賀さんは技術者ではない中で、独自の植物工場をどのように創り上げていったのでしょうか?
古賀:植物工場の技術の源泉は「施設園芸」です。施設園芸の種苗や技術の種は、実は日本とオランダにしかないんです。そのため、創業時から研究チームの多くは日本人かつ農業や植物工場の経験者です。現在では研究チームが約30名まで拡大しましたが、半数以上が日本人です。
もう一つやったことは、日本にいる農家さんや専門家に質問しに行きました。「そもそもハチはどういう生き物なのか?」「グリーンハウスではハチはどのように飛んでいるのか?」「なぜ植物工場では飛ばないのか?」など根本的な疑問を徹底的にヒアリングしていきました。ただ、そういう質問に対する明確な答えを持っている人はいないので、様々な人との会話の内容からピースを繋ぎ合わせ、どうにか自社の技術を確立してきました。
有馬:テック系のスタートアップで起業後にゼロベースで技術を創り上げるスタイルは珍しいですね。
古賀:そうですね、テック系のスタートアップは、「既に存在する技術をどう商業化するか」というテクノロジーアウトの発想になりますよね。
しかし、Oishii Farmでは逆の発想で、「顕在化しているニーズをどうテクノロジーを使って解決していくか」というマーケットドリブンの発想ですべてを進めていきました。私が技術者ではなかったというのも影響しているかもしれません。
その分研究開発に時間もかかりましたが、「確実にこれを作れば売れる」という出口がある状態でやっていたというのが、他のディープテックとは異なるかもしれません。
有馬:おっしゃる通りディープテック領域では技術ドリブンの考え方が多いので、マーケットドリブンで進めていくのは成功のカギの一つだなと感じました。
「イチゴといえばOishii Farm」の世界をつくる
有馬:米国以外の海外展開も考えていますか?
古賀:世界中にこの植物工場を立ち上げて、いち早く「イチゴといえばOishii Farm」というブランドを確立していきたいです。
日本の「あまおう」を見ると分かるように、一度強いブランドが確立すると、他のイチゴがそれを超えることは容易ではありません。しかし、海外では日本のあまおう的なブランドは私の知る限り存在しません。なので、そこをまず取りに行く。そして、イチゴ以外の農作物の栽培にも取り組み、「あの会社が作った○○だから美味しいに違いない」というふうに横展開していきたいと考えています。

21世紀は食・農業・カルチャーの日本
有馬:日本が世界で勝つために戦うフィールドは、やはり農業や食分野でしょうか?
古賀:はい、植物工場以外でも農業や食の領域は全体的に他国に対する優位性がある数少ない領域だと思います。あとはカルチャーや観光ですかね。
大事な観点としては、今の日本は人的リソースの優位性は他国に比べてないわけです。つまり、限られたリソースの中で勝っていく必要があります。そうなると、すでに日本が強い領域かつグローバルで市場が立ち上がってくる領域で戦うことが、日本の勝機だと思います。
食領域は日本が既に世界で大きなアドバンテージを持っているため、なかなか短期的に他国が追いつけるものではありません。20世紀は製造業やエレクトロニクスで世界の覇権を握った日本ですが、21世紀は「食や農業やカルチャーの日本」になっていくのではないかと思います。
有馬:私も日本の食農分野は世界で勝てる領域だと確信していますし、キャピタリストとしてアグリフード分野のGAFAを日本から生み出すために、日々活動しています。
古賀さん、本日はお忙しい中、お話しいただき、ありがとうございました!Oishii Farmのさらなる世界での飛躍を願っています。