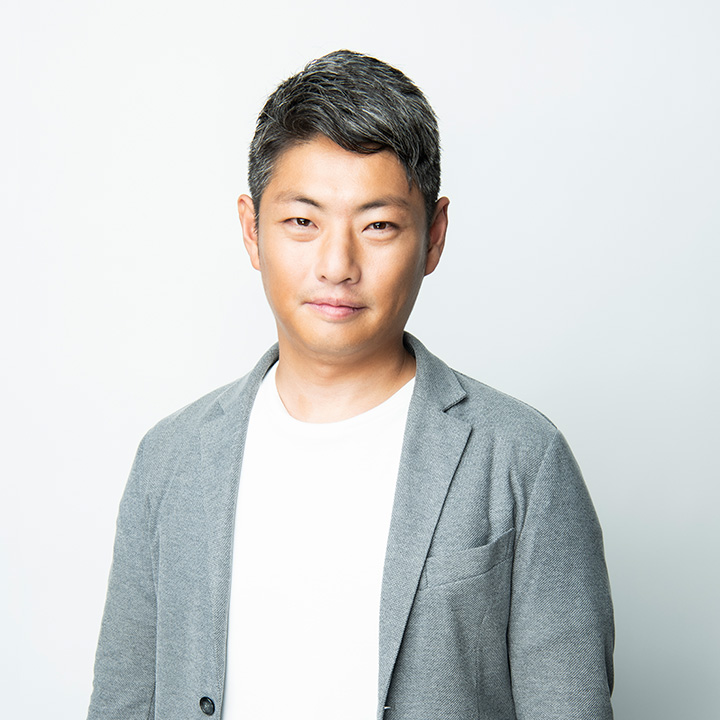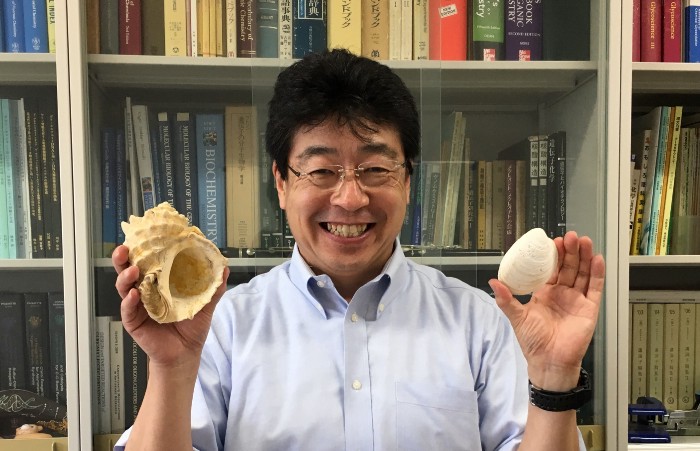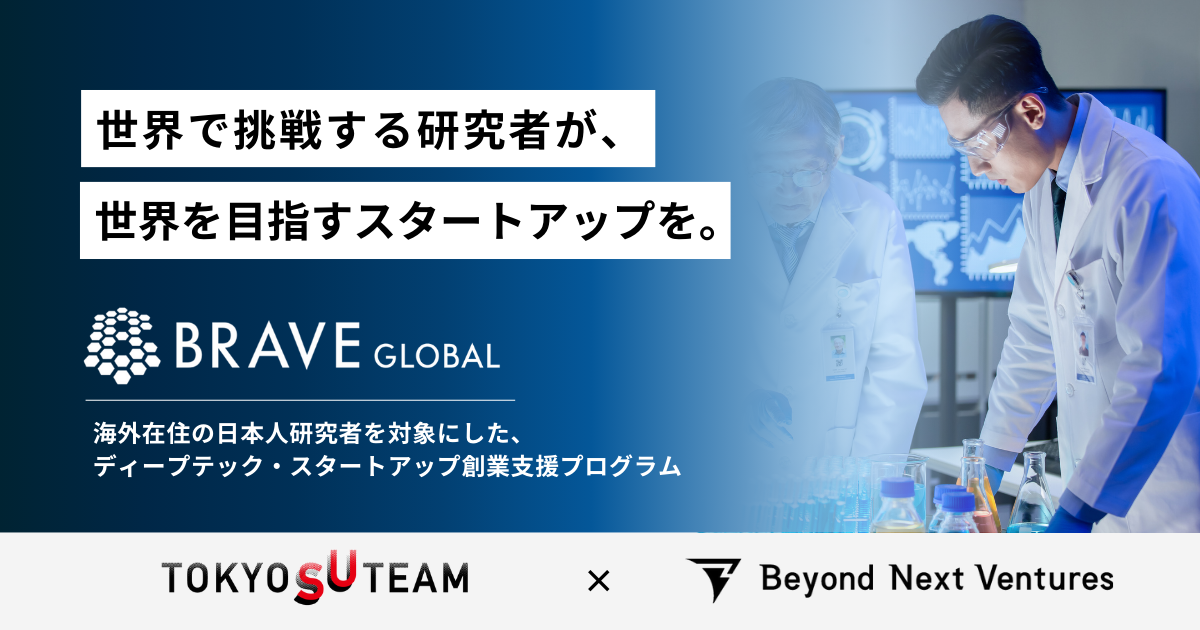「儲かること」の重要性を説く、医師起業家でアイリス株式会社 取締役 副社長の加藤浩晃氏。
最新の医療ビジネス業界の動向からスタートアップ経営における大切な考え方まで、Beyond Next Venturesパートナーの橋爪が伺いました。
【Podcastでも好評配信中です!】
プロフィール

アイリス株式会社 共同創業者・医師
加藤 浩晃 氏
医師、MBA in Finance(一橋大)、元厚労省。専門は遠隔医療、医療AIなどデジタルヘルス。眼科専門医として1,500件以上の手術を執刀、遠隔医療やAIなどデジタルヘルス関連事業を開発。医療・ヘルスケアビジネスに必要な「医療現場」「医療制度」「ビジネス」の3領域を経験し横断的に理解する数少ない存在であり、医療・ヘルスケア領域全般の新規事業開発と支援を行う。
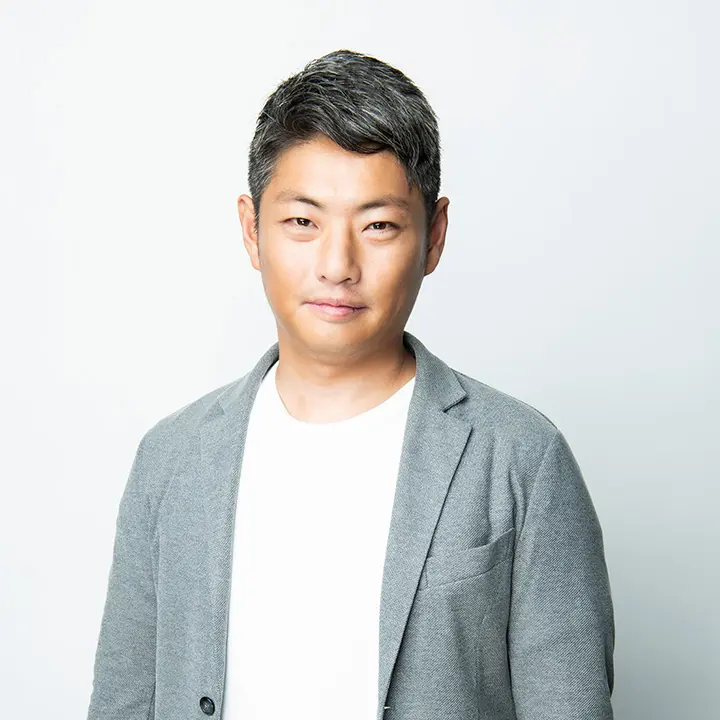
Beyond Next Ventures株式会社 パートナー
橋爪 克弥
2010年ジャフコ(現ジャフコグループ)入社。産学連携投資グループリーダー、JST START代表事業プロモーターを歴任し、約10年間一貫して大学発ベンチャーへの出資に従事。2020年に当社に参画し、医療機器・デジタルヘルス領域のスタートアップへの出資を手掛ける。2021年8月に執行役員に就任。投資部門のリーダーを務めるとともに、出資先企業のコミュニティ運営を統括。主な投資実績はマイクロ波化学(IPO)、Biomedical Solutions(M&A)、Bolt Medical(M&A)等。サーフィンが趣味、湘南在住。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了。
目次
最新のヘルスケア業界の傾向
橋爪:まずは2024年を振り返って、大きな変化などはありますか?
加藤氏:デジタルヘルス領域の細分化が進んでいると強く感じています。2016年頃までは「遠隔医療のDtoDプラットフォームを作ろう」といった大きなビジョンを掲げるスタートアップが多かったのですが、最近は「特定の診療科向けのオンライン診療」など、よりターゲットを絞り込む傾向が強まっています。たとえば、「産婦人科医専門の人材紹介」や「女性医師に特化したキャリア支援」などが挙げられ、このような現象を私は「形容詞が増えている」と表現しています。
細分化の背景には経営者の実体験を通じた課題意識があることはよく理解しています。しかし一方で、その市場規模の大きさや儲かるか否かという話をしている人が減っているように感じます。
また、リスクマネーの流れも変わりました。2016年頃はリスクマネーが多く、私が沖山先生と共同創業したAI医療機器スタートアップのアイリスも大きな夢を掲げて創業することができました。
しかし最近は、デジタルヘルス系のスタートアップも増え、1社へのリスクマネー供給量も少なくなり、その結果として課題の粒度も小さくなっていると感じます。デジタルヘルス市場の成長に伴う変化でもあるので、ちょうど今が過渡期で、新たなフェーズに進みかけている状況なのかなと。
橋爪:確かに私も細分化のトレンドはとても感じています。以前は「デジタルヘルスで薬事承認を初めて取ろう」「保険適用をやっていこう」といったビジョンを掲げて資金を集める会社が多かったです。それが今は承認事例や保険収載される事例も出きているため、それをどうやって横に広げていくのかという事業に変化していますね。
加藤氏:最近はVCも承認を取れる前提で起業家と会話していることが多いと思っていて、「作った後に売れるのか」といったコミュニケーションを取ることが多くなっていると感じます。本音を言うとVCの方も儲かりそうな会社に出資をしたいわけじゃないですか。私自身も医師として起業をした経験があるので、課題解決をしたい想いを持って起業することは理解できる一方、「どうやって儲けるのか」という論点が抜けている傾向が強まっている点に課題を感じていますね。
2025年以降のヘルスケア市場のM&A戦略と資金の使い方
橋爪:2025年以降のヘルスケア市場はどうなると思いますか?
加藤氏:まずは研究開発型のモデルが厳しい状況になってきたのでは、という点です。バイオ領域では今も補助金の支援があったりしますが、デジタルヘルス領域ではリスクマネーへの熱がそっと下がっている感覚ですね。その背景にはやはり「本当に売れるのか?」が厳しく問われる時代になっているからだと思います。
反対に、これからよりブームが来そうだと感じているのは「病院のワークフロー改善×生成AI」です。すでに海外では、病院の業務効率化にAIを活用する動きが加速しており、日本でもこの流れが入ってくると考えています。病院業務のデジタル化が進むことで医師の業務負担を軽減し、より高度な医療に集中できる環境が整備に繋がるでしょう。
これはSaaS型なので積み上げ形式で安定的にお金が入ってくるため、成長の曲線が描きやすい。ヘルステックのような長期間の研究開発を経て、さらにその期間は売上がゼロというJカーブを描くモデルではなく、導入初期から売上を積み上げながら成長していく点がリスクマネーを集めやすいです。
出口戦略を最初から考えてほしい
加藤氏:ここで私から、起業家の皆さんにお伝えしたいことが1つあります。それは出口戦略をあらかじめ考えておくべきだということです。つまりM&Aなのか、IPOなのかを意識して経営しないと、いざという時に決断できません。実際に私は2017年11月にアイリスを創業し、2018年4月にはどっちのモデルにするかの最終的な意思決定をしました。基本的に最初から上場モデルでやろうとは決めていたんですが、海外のモデルを参考にしてM&Aで売却する際のイメージもしていたのです。
なぜこの話をしたのかというと、2025年は冒頭に話した「細分化された事業」が集約される流れになると想像していて、それに伴ってM&Aが必ず盛り上がると考えているからです。海外の医療機器開発では、大体8-10名でプロダクトを作って売却することが多く、SaMDのような事業態であればこのような最適解を1つは考えておくべきだと思っています。
橋爪:確かに、以前と比べると小ぶりな事業が増えている中で、それらをロールアップしてまとめる流れはこれから来るかもしれませんね。

加藤氏:あとは「調子がいいな」と思った時に会社を売る決断力が問われます。これから医療機関DXが絶対的に進んでいくことは見えているので、開発にかける時短のために大手企業がM&Aをする考えも当然のように生まれるでしょう。
実際に、大手企業が自前でスタートアップと類似のサービスをリリースするといったことも起きています。恐らくこのようなケースの裏側には、大手企業が買収の話をスタートアップに持ち掛けている可能性を想像していて、その際に経営者が「もっとやれる」と思い、売り時を逃してしまっていることもあるのかなと。
「医師総事業開発時代」はくるのか
橋爪:話が変わるのですが、これからの医師のキャリアについて今後どのように変化していくと思いますか?
加藤氏:「2030年に医師30万人、総事業開発時代」ということを勝手に言っていて、臨床をしながら医師としてのノウハウを事業に活かす時代が来てほしいと思っています。例えば企業と連携し、医療機器の開発やデジタルヘルスサービスを展開するなど、当たり前に医療とビジネスの融合が進んでいくことを想像しています。
現在のクリニック経営において、100%保険診療を行うとインフレに対する耐性が低くなり、経営が厳しくなるケースが増えており、私のクリニックでは一部自費診療を取り入れるようになりました。メインは産婦人科なのですが、2割程度は美容皮膚科の自費診療を取り入れて経営していて、インフレにも対応できているのでやってみて良かったと感じています。
実際にやってみた気付きは、自費診療で受診されていた方が今度は産婦人科で受診したり、その逆のケースも起きていて、良い循環が起きています。他には電子カルテや自動精算機を取り入れて、スタートアップ企業とタッグを組んでオペレーションを考えて運営に繋げることもやっています。
このように、保険診療100%のクリニックではなくなることが、1つ目の変化として起きることだと思っていて、そこを目指したクリニック運営や医師自身のキャリア形成を考える必要があると思います。これから医師は何者かにならないといけない時代が来る、そう考えた時に開業医の方の例で挙げると、産業医をしてみたり、予防医療やアンチエイジング、他にはパーソナルドクターなど選択肢は多くあり、企業と関わらなくてもやり方はたくさんあります。
技術×価値観の変化でイノベーションは起きる
橋爪:医療・ヘルステックの技術の観点ではいかがでしょうか?
加藤氏:私の立場的に医療に関する技術の回答が求められていることは重々承知しながら回答すると、技術というよりマインドの方がこれから重要になっていくと考えています。
VRやARグラスが軽くなったといった進化はあるかもしれないですが、すでにサービス化されているものが格段に進化することは難しいと思っています。一方で、新しく研究開発されたものが来年・再来年にサービスの領域まで進むことはないとも思っているので、技術には今はあまりフォーカスしていないのが正直な回答です。
それよりも、すでに存在する技術を使う側の医師のマインドセット、つまり価値観が変わることが本当のイノベーションにつながると考えていますし、先ほどのキャリアの話にも繋がると思っています。

橋爪:価値観の変化が、医療業界の進化を後押しするということですね。
加藤氏:価値観を変えることは簡単ではないですが、1960年代の労働市場では「女性は家庭に入る」考え方が一般的だったところから、「女性も労働市場に参加できる」ムーブメントが起き、結果として価値観が変わり、社会全体の構造が変わりました。
医療業界においても同様にSaMDや生成AIによって外部環境が変わってきています。この環境を上手く利用し、デジタル技術の活用が「当たり前」になるための地道な啓発活動をするのも1つの方法ですし、むしろ一気に変えていく方法もあると思っています。医師会もそろそろ世代交代が起きると思っていて、それに伴い大きなムーブメントが起きると、世の中が変化しやすい流れになるのでないでしょうか。
先ほど女性の社会進出の例を挙げましたが、食洗器や掃除ロボットが発達したから女性はより社会に出やすくなった訳ではないですよね。つまり価値観の変化なんです。
この環境を医師に置き換えた時に、今はテクノロジーの発展が著しい状態なので、あとは価値観を変化させていきたい、そんなことを考えて今度、書籍も出版しようと思っています。
橋爪:単に新しい技術が登場するだけではなく、それを受け入れる側の意識変革が伴わないと、本当の意味でのイノベーションは生まれないということですね。
加藤氏:少し角度が変わりますが、私は業種間のタイムマシン経営があると考えていて、それが医療業界にとってはプラスに働くと思っています。なぜなら医療業界はトレンドが来るのが一番遅いから。圧倒的にトレンドが早いのはエンタメ業界で、エンタメ業界の流行から他の業界にトレンドが移り、巡り巡って最後に医療業界にくるのがおおよその流れになっています。
医療業界がただトレンドに反応するのが遅いと思われるかもしれませんが、見方を変えるとトレンドが来るまで準備ができるんです。よって私は医師の価値観の変化についても今か今かと待ち構えている、そんな感覚でいます。
儲かることが、社会課題の解決への一番の近道
橋爪:最後に医療スタートアップやこれから起業しようと考えている方に向けて、成功のためのアドバイスをお願いします!
加藤氏:一番重要なのは「本当に儲かるのか?」を徹底的に考えることです。多くのスタートアップが「社会課題を解決する」という目標を掲げますが、それだけでは持続可能なビジネスにはなりません。よく起業を志されている方から事業のアイデアを伺うのですが、「儲かるのかな」と感じることも度々あります。
本来は売上の中から研究開発費を捻出して開発をするのですが、創業当初はそもそも売上がない。だから売上が出るまでの時間を短くするために投資をしてもらう訳で、そのためには「将来これくらいの規模になるから、今お金を出してください」とお願いをしにいくのが筋だと思っています。なので、儲かることが、お金を出してもらうためには絶対的に必要なことなんですよね。
つまり何が言いたいかというと、開発にフォーカスしすぎず、開発したサービスをどのように売ってどのようにお金を受け取るのか、「How」の部分まで考えることが必要です。サブスクリプション形式なのか、都度課金なのかによって、当然のことながら売上の作り方も変わってきます。他にはサービス販売について、仲介業者が入るのか否かや集金のタームによってもお金の流れが変わるのでとても重要なポイントです。

橋爪:おっしゃる通り、プロダクトだけでなくどうやってお金もらうのかは持続可能な経営を見据えた際にとても重要ですね。
加藤氏:もちろん途中でピボットしてもいいと思っているのですが、軽くでもイメージしておくことがとても大事です。
ここまでいろいろ言いましたが、私がとにかくお伝えしたいことは「儲かる事業をやろう」、この一言に尽きます。「ボロ儲けできると思える事業だ!」と思っても、ちょっと儲かるくらいが現実だと思っているので、ぜひ大きく考えて挑戦してほしいです。
橋爪:社会課題を解決するためにも、みんなで儲かるビジネスをしましょう!加藤さん、貴重なお話ありがとうございました!