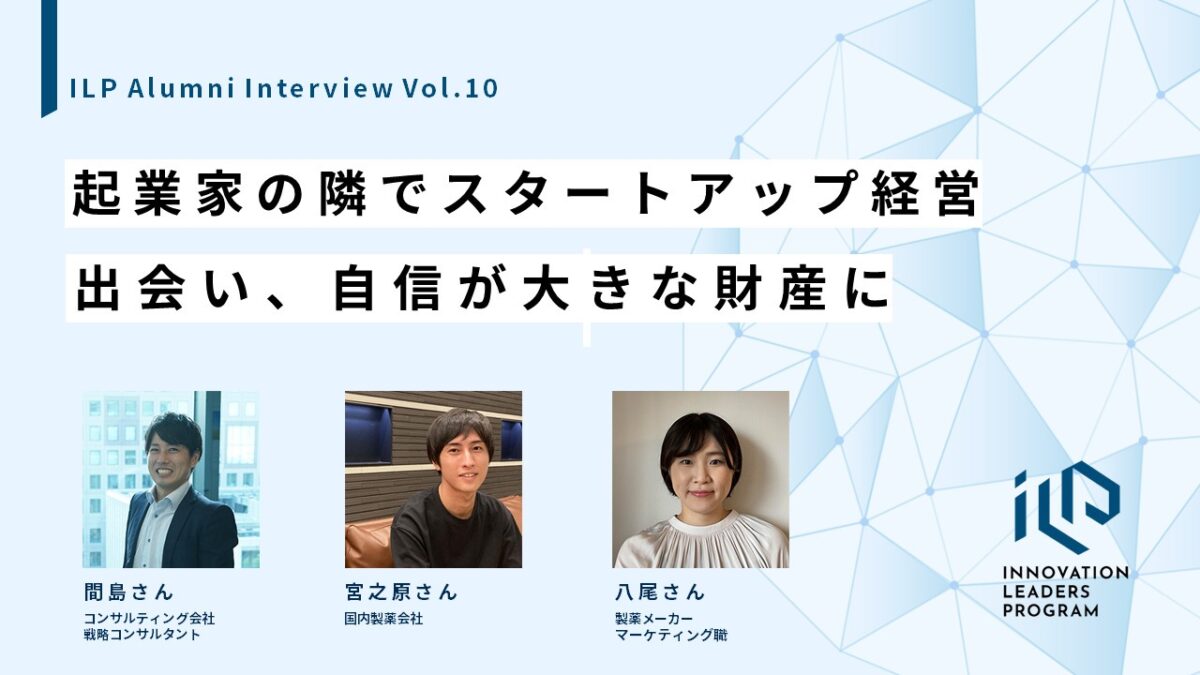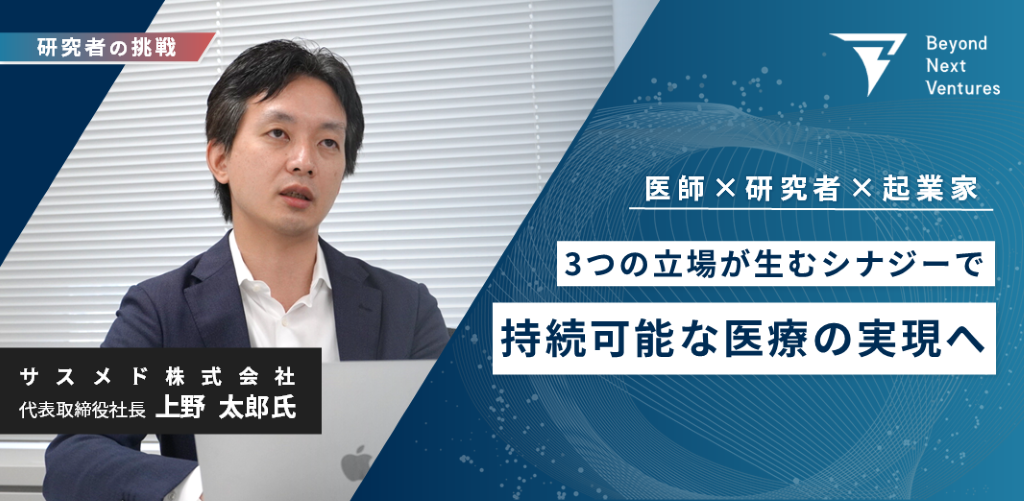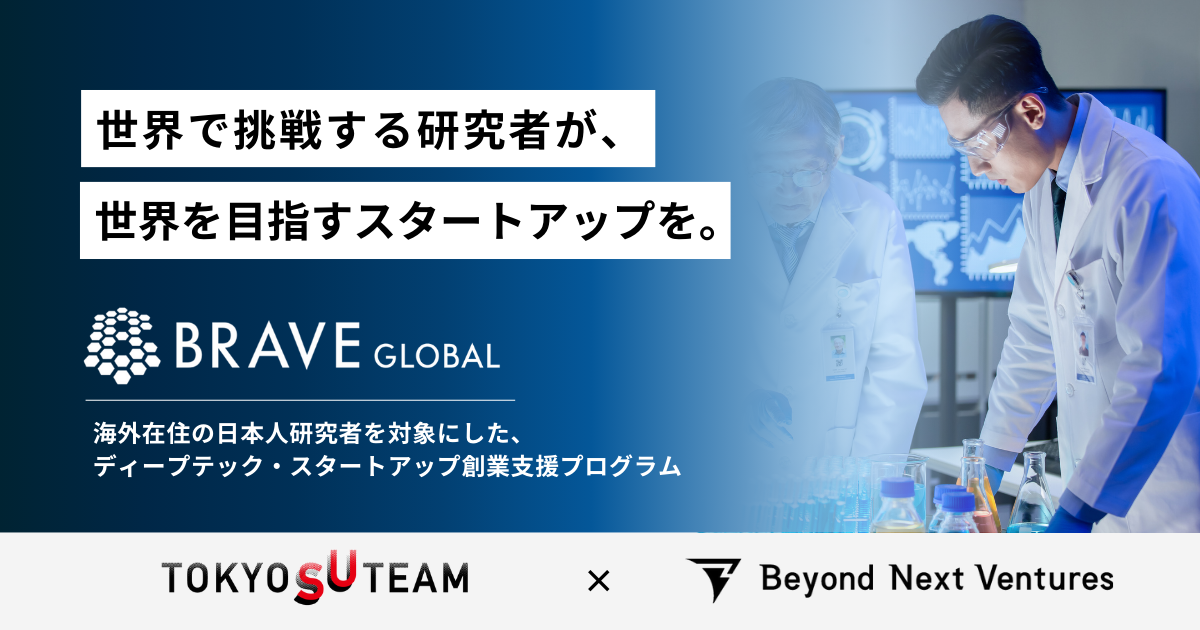Beyond Next Venturesパートナーの有馬です。今回はフードテックを語る上で欠かせない方々をお呼びし、フードテックにおける課題や未来について語ります。
今回お呼びした皆さんは5月に開催されたTECHNIUM Global Conferenceでも登壇をしていただいており、そのままの熱量で熱く、深く語り合っていただきました。ぜひご覧ください。
【Podcastでも配信中です!】
プロフィール

株式会社UnlocX 代表取締役 CEO
田中 宏隆 氏
パナソニックを経て、McKinsey & Companyにてハイテク・通信業界を中心に8年間に渡り、成長戦略立案・実行、M&A、新事業開発、ベンチャー協業などに従事。 17年シグマクシスに参画しグローバルフードテックサミット「SKS JAPAN」を立上げ。食に関わる事業開発伴走、コミュニティづくりに取り組む中で、食のエコシステムづくりを目指し2023年10月株式会社UnlocX創設。スタートアップ2社の社外取締役を務めている。

株式会社AlgaleX 取締役副社長 CFO
日高 英祐 氏
新卒で商社に入社後、穀物取引を行う米国事業会社の企業再建プロジェクトに従事。2018年より米国の現地で取締役としてプロジェクトを推進。デリバティブ取引管理・信用リスク管理・貿易金融・債権回収・監査業務・訴訟などを中心に職務経験を有する。2021年のAlgaleX社創業時より現職。主に営業と管理を担当。藻の研究開発中にできた将来的に天然魚の代替となることが期待されている原料「うま藻」を販売。神奈川県生まれ、沖縄県在住。

株式会社MiL 代表取締役 CEO
杉岡 侑也 氏
大学受験に失敗し5年間フリーター。人生どん底から、環境に恵まれ社会人として復活した経験より、”人の可能性は無限大” を証明するため起業。2016年に大学生のキャリア支援を行う株式会社Beyond Cafeを創業し、1年間に1万人100社が利用する企業へと成長。2018年には2社目となる、中小企業支援、非大卒者のキャリア支援を行う株式会社ZERO TALENTを創業。数多くファウンダーとして事業の立上げを経験する中で、人の可能性を突き詰めるためには、身体と心のパフォーマンスを最大化させる重要性を痛感。その想いから2018年に妻とシェフと3人フード×ヘルスケアスタートアップ株式会社MiLで創業。現在は子供向けの食品ブランド「カインデスト」を展開。

株式会社YUMRICH 代表取締役 CEO
柳父 豊 氏
家事代行のスタートアップで社長室長を経験後、インテリア会社Rignaの企業再生のため社長就任。企業再生後にプライム上場企業に創業者の株式を売却(M&A)。グループ最年少社長になる。さらに、PEファンド投資先の美容室チェーンAshantiで社長を務めた後、植物性のミルクからアイスを作る、プラントベースアイスクリームの株式会社YUMRICHを創業。経営管理からマーケティングまで、ビジネスサイド全般を担当している。

Beyond Next Ventures株式会社 パートナー
有馬 暁澄
2017年4月丸紅入社。穀物本部にて生産から販売までのアグリ全般に携わる。また、アグリテック領域のスタートアップ投資チームを立ち上げる。2019年に当社に参画し、アグリ・フードテック領域のスタートアップへの出資・伴走支援に従事。2022年にパートナーに就任。農林水産省や大企業と連携し、産学官連携プロジェクト(農林水産省「知」の集積プログラム、「フードテック研究会/ゲノム編集WT」代表、スタートアップ総合支援事業「AgriFood SBIR」PMなど)にも取り組む。目標はアグリ・フード領域のGAFAを生み出すこと。慶應義塾大学理工学部生命情報学科卒業。
目次
フードテックの成功事例に学ぶ「モノ+コト」提供の価値
有馬:杉岡さんは事業を始めて約7年、ブランド開始から5年程で社員数40名まで拡大されたとのことですが、その軌跡が非常に気になります。
杉岡氏:私たちの事業はコロナ禍が始まる直前にスタートしました。まず着目したのは、離乳食が子供を持った家族にとって「避けては通れない壁」であるという事実です。特に初めての育児では、離乳食の知識を学び、アレルギーの不安を解消するなど、多くのタスクに追われます。
しかし、これまでの食品メーカーはすり潰した人参を時短で提供するような物質的なサポートしかできていませんでした。私たちは、お客様が抱える不安や「わからない」という段階から、インターネットを通じてサポートできないか、というごく自然な疑問から事業を始めたのです。今では離乳食デビューをする10人に1人の方が、私たちが開催する離乳食セミナーに申し込んでくださいます。
有馬:プロダクトの手前にある「教育」や「誰もが学べる環境作り」がテーマになっているのが面白いですね。インサイトを掘り下げると、「お母さんがお母さんになるための投資」といった課題が、昔から解決されないまま残っている。子供の成長に合わせて常に新しい課題にぶつかるのに、そのノウハウが十分にシェアされていないのが現状です。
杉岡氏:本当にそうなんです。「父親が父親になるための投資」も同様で、これまで出版業界などが解決しようとしてきた領域を、私たち食品業界が新しいアプローチで解決していく、という発想です。
価値を最大化するマストハブとナイストゥハブ
杉岡氏:なぜベビーフードを選んだのか、ビジネス的な側面からお話しすると、その市場性にあります。例えば、スイミングスクールや学習塾に通う子供は多いですが、100%ではありません。
しかし、離乳食は、全ての赤ちゃんが必ず通る道です。「この子供たちと絶対に出会う」と決めるのであれば、この領域に参入するのが最も効率的で合理的だと考えました。
有馬:今のお話を聞いて、杉岡さんのプロダクトは「誰もが通る道」にあるので、「マストハブ(必需品)」に近いと感じました。ここから議論を発展させたいのですが、フードテックやアグリテックを、いかにこの「マストハブ」に近づけるかがスケールアップの重要なポイントなのではないでしょうか。一方で、「ナイストゥハブ(あったら嬉しいもの)」として成功する道もあると考えています。
YUMRICH(以下、ヤムリッチ)を運営する柳父さんは、ステージとしてはこの中で一番若いですがどのようにお考えでしょうか。
柳父氏:私たちは「贅沢なひとくちを、すべての人に。」をキャッチフレーズに掲げており、マストハブを目指しつつ、まずはナイストゥハブから始めています。もちろん、アレルゲンフリーが必須な方や、宗教上の理由で動物性が取れない方にとってはマストハブになり得ますが、事業全体としては贅沢品、つまりナイストゥハブだと考えています。
田中氏:その「ナイストゥハブ」を言い換えると「ラグジュアリー」となるかもしれません。ラグジュアリーは明確な目的がなくとも「持ちたい」「体験したい」という欲求から生まれ、高単価になり得ます。これはスケールのための一つのアプローチです。
一方で「マストハブ」も分解して考えることができます。一つは、離乳食や高齢者の嚥下食のように、多くの人が必ず通る「可視化されたマストハブ」。もう一つは、私自身も経験したアレルギーや、女性のバイオリズムに対するソリューションのように、当事者にとっては絶対的な必需品であるにもかかわらず、世間では見過ごされがちな「隠れたマストハブ」です。
杉岡氏:田中さんのお話は非常に的確で、まさにその通りだと感じます。MiLの製品も、当初はなかなかスポットライトが当たらなかったという意味では「隠れたマストハブ」だったのかもしれません。近年市場が拡大している冷凍食品なども、こうした隠れた生活者のインサイトが表に出てきて、「確かにそういうライフスタイルは良いよね」という共感から大きな市場を創り出した例だと思います。
有馬:AlgaleXの日高さんの事業も、人が必要とするDHAを生産している点ではマストハブに見えますが、廃棄物からアップサイクルした藻を原料に「醤油」という製品で美味しさを前面に出して販売している。これはナイストゥハブの領域ですよね。
日高氏:はい。ただ原料の製造コストや性質上、どうしても最初の戦略がプレミアム、つまりラグジュアリーになってしまう点は課題だと感じています。よってマス向けの価格設定が難しく、どうしてもナイストゥハブの領域から始めることになり、まだそこから先の展開が見えていないという悩みがあります。
「アイス可愛い」が行列をつくる?フードテックにおける感情デザイン戦略
柳父氏:このようにナイストゥハブとして事業を行う上で、私は「クリエイティブ」が非常に重要だと主張したいです。フードテックは技術主導になりがちですが、消費者は必ずしも技術そのものを求めているわけではありません。
先日開催されたイベントで、私たちのブースに開始5分で数百人の大行列ができ、最終的に運営から営業規制が入るほどでした。ブースに並んでくれたのは親子連れや他の出展者の方々でしたが、彼らを惹きつけたのは技術の機能性ではありませんでした。
ポスター1枚のデザインで、子供たちが「アイス食べたい」、若い女性たちが「可愛い」と感じて「並ぼう」となる。そう思わせるクリエイティブを提供できたことが勝因だと考えています。個人の消費者が、製品を手に取る際にどう感じるか、という視点が大切です。
有馬:なるほど。マストハブとナイストゥハブの要素を融合させ、さらにクリエイティビティを重ねることで、顧客の心を掴みにいったわけですね。
柳父氏:さらに戦術的な話も付け加えると、あえて行列をきれいに捌かず、一人ひとりと会話しながら丁寧に提供しました。これにより顧客体験が向上し、さらに「列が列を呼ぶ」という日本人の特性を刺激しました。結果として、行列は5倍、6倍に膨れ上がったのです。
有馬:そもそも、なぜヤムリッチは数ある製品の中から「アイス」で事業を始めたのですか?
柳父氏:理由は単純です。一つは、成功事例を真似ることから始める、という私のスタンスです。先行していたエクリプスフーズ社がアイスで評価を得ていたので、私たちもまずアイスから着手しました。先行事例がないと、特に日本では新しいものを受け入れてもらいにくいですし、私たちも説明しづらい。そしてもう一つは、単純に私がアイスクリーム大好きだったからです。
日高氏:柳父さんの話は素晴らしくとても参考になった一方で、当社には市場に関する悩みがあります。
先ほども触れましたが当社の場合、原料の関係で大きな市場への流通が難しいという現実があり、高価格帯の商品になってしまいます。しかし市場に流通させると、小売店で売れる調味料の大半は例えば醤油1リットルのようなマストハブ商品で、どんなに美味しい調味料でも売れる割合は1割程度となっているのが実際の厳しい現実です。そのため市場がどうしても限定されてしまう、という課題があります。
恐らく他のスタートアップも事業立ち上げの戦略に“ラグジュアリー”を選択した場合、狭い市場に入り込んでしまうため、その後の拡販の壁にぶつかると思います。もちろんクリエイティブでカバーできることもあるとは思うのですが、流通の中ではクリエイティブを発揮する余地も少なく、販売店の中でもメインの施策にはならない点が常に課題となっています。
私たちがこだわっている原料から導き出される最適解が、最初はラグジュアリーなナイストゥハブになってしまう、そこは致し方ないと思いつつ、そこからどうやって大きく飛躍させるかが本当に大きな課題です。
有馬:たしかにそれは切実な悩みですね。
「スケール」の壁:スタートアップが直面する複合的な課題
有馬:さて、ここまで各社の戦略や悩みを伺ってきましたが、最終的には事業の「スケール」という話に行き着くかと思います。まずは杉岡さん、いかがでしょうか。
杉岡氏:私も「スケール」という点に立ち戻るべきだと考えています。日高さんがおっしゃったように、スタートアップが特定の領域に絞って戦略をとるのは当然ですが、それだけではスケールが難しい。複数の戦略を組み合わせたり、段階を踏む必要があります。この「スケールへの道筋」を業界としてどう見出していくか。これは、多くのチャレンジャーが成功を収める上で、避けては通れない非常に重要なテーマだと思います。
有馬:成功事例がまだ少ないですよね。私が思うに、フードテックの成功には2つの鍵があります。一つは「いかに生き残るか」。食は文化なので人々の生活に浸透するには時間がかかります。10年、20年と辛抱強く取り組む中で、必ず花開く時が来る。そこまで耐えられるかが重要です。二つ目は「ひたすらPDCAを回せるか」。顧客の嗜好は常に変化します。長期的に取り組むメンタルと戦略、そしてそれを支える資金力と意思決定能力が問われます。
田中氏:有馬さんがVCの立場で「耐久」の重要性を語るのは非常に勇気づけられます。食のスタートアップはR&Dから製造、流通、マーケティングまで、なぜ全てを自前でやらなければならないのか。これは非常に効率が悪く、リアルな「モノ」を扱うがゆえに爆発的なスケールが難しい構造になっています。
柳父氏:私も今最も悩んでいるのは、この「生き残り」のハードルの高さです。私たちはVCから調達せず自己資金でやっていますが、OEMで商品開発しようとするとロットが大きすぎて支払いも保管もできない。結局、家庭用のアイスメーカーをイタリアから買って自宅で製造するところから始めました。
日高氏:私たちも最初の1年間は自己資金でした。「うま藻」という世間一般には理解不能なものを研究開発できたのは、県の使われなくなった施設が解放されていたという、再現性のない幸運があったからです。それがなければ、プロトタイプを作るだけで数百万、数千万円が飛んでいく世界でした。
柳父氏:さらに、いざ資金調達しようとするとジレンマがあります。経験を積むほど、投資家に対するIRR(内部収益率)を達成できる確証がない限り、安易に資金を受け入れられないという倫理観が生まれる。かといって、価格を下げるために大規模な設備投資(キャペックス)に踏み切れば、経営の柔軟性が失われる。このバランスが非常に難しいのです。
杉岡氏:そうですね、少し異なりますが当社についてはベビーフードという商品特性上、そもそも市場規模(日本の出生数は70万人を割っている)が限定的な中で、どうユニコーンを目指すのかという課題もあります。
フードテック成功の鍵は「自社だけでやらない」こと
田中氏:私は、スケール化のヒントは「単独でやらないこと」、つまり「群」になることだと考えています。ヨーロッパのスペインには、一社の勝ち組を作るのではなく、業界全体で多様なプレイヤーを支え、産業を形成する「クラスター」という中間組織が存在します。開発はここのラボ、販売はあの企業、というように業界全体で分業するモデルです。
有馬:日本にもパーツは散らばっていますね。
田中氏:はい。それらを連結させればいい。私が面白いと思うのは、杉岡さんのように自社ブランドを持ちながら、外部のメーカーや原料メーカーと組んで新しい価値を生み出す動きです。スタートアップが業界を束ねるような、オーガニックではないスケール化も可能ではないかと考えています。
日高氏:地方には、当社が利用している県の施設のように、各都道府県が設立し、今は使われていない「謎の資産」や、優良な中小企業の無形資産が眠っています。そういったものをうまく寄せ集め、パッチワークしていけば、何か新しいものが生まれるはずです。
挑戦を支え、10年耐えるための資金調達戦略
柳父氏:解決すべきは、大手と中小、両方の経営課題です。大手食品企業はガバナンスが保守的でAI時代に適応した成長戦略を描けていない。一方で多くの中小企業は、大量の資産を持ちながら経営ガバナンスが効いていない。私たちのようなインターネット中心の経営を学んだ人材が、これらの変革に流入していくべきです。
日高氏:しかしガバナンスには難しさもあります。労働基準などを厳格に適用することで、逆に事業が立ち行かなくなる中小企業を実際に見てきました。単純な合併では生産性は上がらず、根本解決にはなりません。
田中氏:私は問題は今後、AIを徹底的に使いこなすことで解決されつつあると考えています。退職者のスキルをAIに移植して「継承」したり、超高速のPDCAを回したりすることで、経営スピードは格段に上がります。アメリカのあるユニコーンは、AI活用で2年かかっていた製品開発を数週間に短縮しました。 スタートアップが持つこのスピード感とAI活用能力で、大企業や中小企業の「資産」にアクセスする。アクハイア(買収による人材獲得)ではなく、資産にアクセスする新しいスキームが作れたら面白い。
柳父氏:そのような挑戦をするためにも、ファイナンスのあり方が重要です。プロトタイプの敷居を下げ、ビジネスパーソンが自分の人件費を確保できるような仕組みが必要です。例えば、メザニンファイナンスや10年タームの長期VCファンド、あるいは大企業ともっと早い段階で連携するような形がなければ、優秀な人材はリスクを取ってこの業界に参入できません。
私と杉岡さんが参加している食スタートアップ経営者の会でも、皆同じ課題を抱えています。プレイヤーはもういるのです。しかし、彼らに手を差し伸べる主体、つまり「一緒にやろう」と言う地方の有力者や、大企業、そして「我々と社会実装しよう」と言う金融機関が現れていないのが現状です。
田中氏:最終的にはやはり「人」だと思います。この業界に、杉岡さんのようなビジネスパーソンがもっと参入してくれる環境を作ることが重要です。コンサル業界のように人材のエコシステムが回るようになれば、日本のアグリフード業界は大きく変わる。本当に皆がこの業界に興味を持って挑戦できる、そういう環境を作りたいですね。
未来を創るスタートアップ経営者たちの挑戦
有馬:今回の議論には、皆さんの野望を伺うという裏アジェンダがありました。最後に、それぞれが伝えたいこととその野望をお聞かせください!
田中氏の野望:持続可能な「エコシステム(出島)」の創造
田中氏:私が目指すのは、持続的に共創を続けられるエコシステム作りです。業界が真に変わるためには、本当の意味での「出島」のような場所が必要だと考えています。ぜひ皆さんで一緒にその実現に取り組みましょう。まずは10月に開催されるSKS JAPANで、具体的なアクションを起こしていきたいです。
日高氏の野望:新原料開発と、そこに至る「仕掛け」作り
日高氏:私たちの最終的な野望は、魚の代替となる新しい藻の原料を生み出すことです。しかし、そこに至るまでには時間がかかります。スケールアップするまでの間に、皆さんと協力して、事業を支える「しっかりとした仕掛け」を構築しなければならないと、今日の議論で改めて強く感じました。この大きな野望をぶらすことなく、そこまでの道のりを皆さんと一緒に作っていきたいです。
杉岡氏の野望:コラボレーションによる「成功の型」の確立
杉岡氏:私が強く思うのは、私たちの世代で、後に続く人たちのための成長成功の「型」を見つけ出さなければならない、ということです。それは個人の努力だけで成し得るものではなく、多面的なコラボレーションの先に見つかるものだと確信しています。スタートアップだけでなく、総合商社、大手食品企業、海外パートナーをも巻き込み、誰もが成功の方程式にアクセスできるインフラを築く。自分の挑戦がその一助となれば、良い人生だったと思えるでしょう。(冗談ですが、田中さんのカバン持ちになるのも野望の一つです。)
柳父氏の野望:日本の食を世界へ届けるグローバルブランドへ
柳父氏:私たちはまだ事業フェーズが若く、アイスクリームの製造コストが大きな課題です。ですから、当面の目標は、大企業をはじめとするパートナーと製造面で連携することです。しかし、それはあくまで手段です。私たちの最終的な野望は、日本から世界に通用する食のスタートアップになること。「ヤムリッチ」というブランドを世界に打ち出し、日本の優れた果物や私たちのPDCA技術を世界に広め、しっかりと外貨を稼ぎたいと決めています。
有馬:みなさんの考え、とても勉強になりました。本日はありがとうございました!