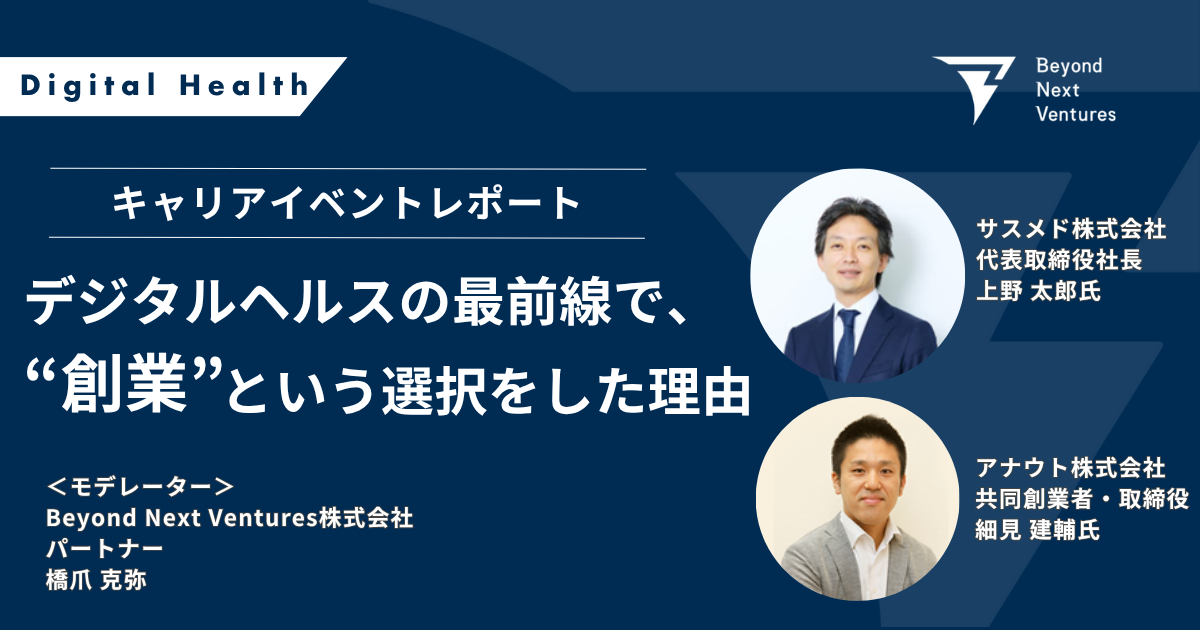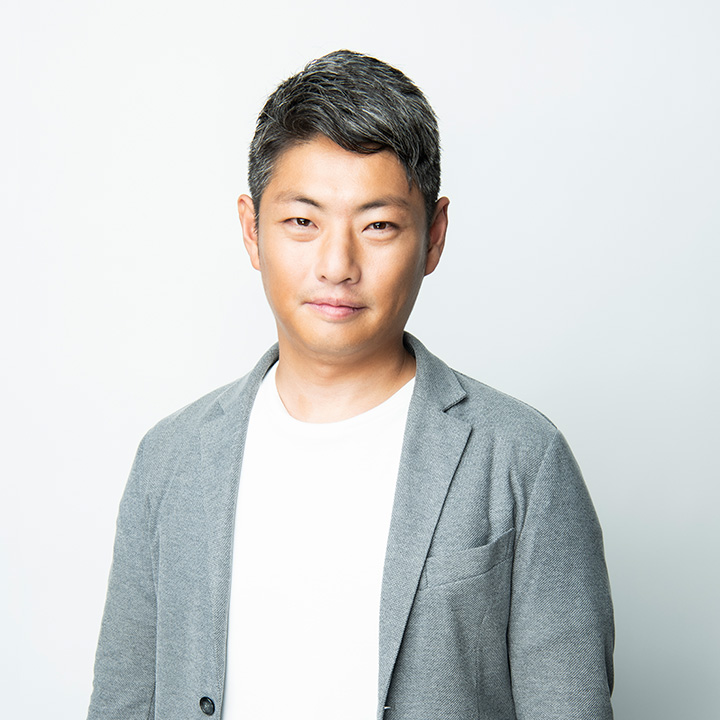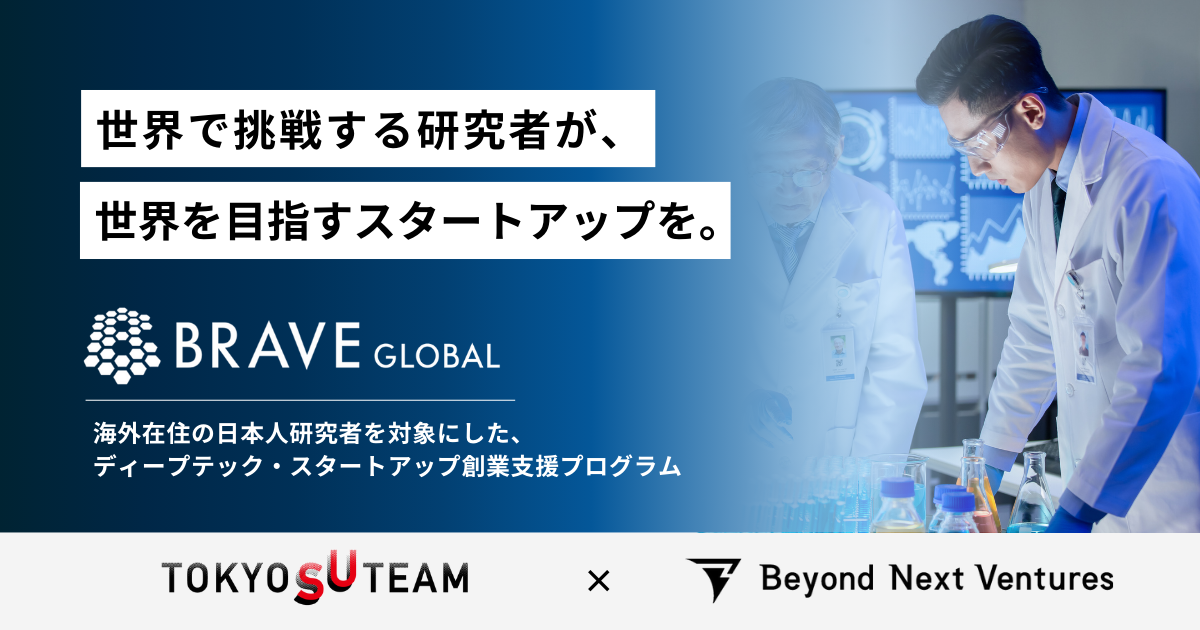Beyond Next Venturesでは、スタートアップやディープテック領域での創業や経営参画を目指す方々に向けた、人数限定のキャリアイベントシリーズを開催しています。今回は「デジタルヘルス」をテーマに、創業初期の実体験に焦点を当てた回を実施しました。
登壇者は、治療用アプリの社会実装に取り組み、日本初の上場を果たしたサスメド株式会社・上野太郎氏と、手術支援AIという未踏の領域で新たな技術開発に挑むアナウト株式会社・細見建輔氏。いずれも医師や戦略コンサルタントとしての実績を持ちながら、あえてスタートアップという不確実性の高い道を選んだ経営者です。
当日は30名を超える参加者が集まり、創業の背景や、直面したリアルな課題について、熱量の高い議論が交わされました。本記事ではモデレーターのBeyond Next Ventures パートナーの橋爪 克弥より、「なぜ彼らは挑戦するのか?」という問いを投げかけ、スタートアップキャリアを考える上でのヒントを抜粋してお届けします。
プロフィール

サスメド株式会社
代表取締役社長
上野 太郎氏
医学博士、医師。精神医学・神経科学分野を中心とした科学業績を多数有し、臨床医として専門外来診療も継続。2006年、東北大学医学部卒業後、都立広尾病院にて初期研修修了。2012年、熊本大学医学教育部博士課程修了。2015年にサスメド株式会社を創業。治療用アプリや臨床試験の効率化推進システムを開発。井上研究奨励賞、武田科学振興財団医学系研究奨励、内藤記念科学奨励金・研究助成、肥後医育振興会医学研究奨励賞など受賞。日本睡眠学会評議員、経済産業省ヘルスケアIT研究会専門委員、日本脳科学関連学会連合産学連携諮問委員

アナウト株式会社
共同創業者・取締役
細見 建輔
PwCにおける公共セクターの財務アドバイザリー、戦略コンサルティング(Strategy&、元Booz&Company)を経て、2020年にアナウト株式会社の外科医との共同創業に携わる。外科医療AIスタートアップの組織構築、財務・事業戦略をリードし、2024年にはPMDAから薬事承認を取得、現在は海外展開に取り組む。東京大学教養学部総合社会科学科国際関係論分科卒、ノースウェスタン大学・テルアビブ大学経営学修士
デジタルヘルスで医療の未来を創る経営者の想い
当日の会場には、デジタルヘルス領域での起業やスタートアップへの参画を真剣に考える、約30名の方にお集まりいただきました。
イベント前半のトークセッションでは、日本初の治療用アプリ上場企業であるサスメド株式会社の上野氏と、手術支援AIという新たな領域を切り拓くアナウト株式会社の細見氏が登壇。立ち上げ・参画へ至った道のりを振り返りながら、それぞれの事業家としての想いが語られました。
コンサルティングファームでの経験を捨てて海外で生活していた際にアナウトの事業、共同経営者と出会い、不思議な縁を感じました。技術や製品の強さはディープテックスタートアップの成功に不可欠です。しかし、良質な技術を持つ全ての企業が成功するわけではなく、最後は人が成功を左右すると思います。日々一層成長する必要性を感じながら経営のAtoZに取り組んでいます。(細見氏)
お二人の言葉の背景にあるのは、医療現場が抱える課題をテクノロジーで解決し、より良い社会を築きたいという熱い想いです。
サスメドの上野氏はがん治療を例に挙げ、人生の最終段階における医療ケアの課題を指摘。「緩和ケアの推進や患者さんの意思決定支援が求められていますが、日本では臨床現場のリソース不足もあって十分な心理的ケアや意思決定支援が行えていないという問題があります。」
日本の終末期医療における緩和ケアの在り方や高額になる医療費への課題観を、実際の医療現場で起きている事例に触れ、サスメド社が取り組んでいる国立研究開発法人国立がん研究センターとの取組事例を紹介しました。
またアナウトの細見氏からは、外科手術の変遷や手術手法の進化を紹介しつつ、手術合併症のリスクを述べました。「論文報告によると、その1/3は認識の不足というところが言われています。内視鏡手術は医師の目に革新をもたらして、ロボット支援手術は医師の手に革新をもたらしました。しかし、この間に入る医師の“認識判断”というところは、まだまだイノベーションが足りてないのが現状です」
課題提起とともに実際にアナウト社の製品のデモ映像も用いて、外科手術における医師の「認識・判断」をAIで支援する方法を参加者に紹介しました。
上野氏、細見氏それぞれの言葉一つひとつに、事業への情熱と、未来への揺るぎないビジョンが滲み出ていました。参加者は真剣な眼差しでその言葉に聞き入る様子が伺え、後半で開催した懇親会では参加者同士の意見交換も活発に行われていました。

スタートアップキャリアの壁を越えるヒント
イベント後半のパネルディスカッションやその後の交流会では、より具体的なキャリアに踏み込んだ会話が展開されました。特に「業界未経験からの挑戦」と「スタートアップ経営の面白さ」というテーマは、多くの参加者にとって自身のキャリアを考える上で大きなヒントとなったでしょう。
ヘルステック業界へ未経験から挑戦する難しさ
アナウトとの出会いを“Connecting the dots”(点と点がいつの間にかつながること)と振り返る細見氏。
とはいえ、“医療”という専門性の高い領域に、バックグラウンドなく飛び込んだことについて「そのハードルをどう乗り越えたか?どう知識を身につけたのか?」という質問があがりました。
問いに対して細見氏は「そこにいれば少しずつ“慣れる”ものだと思っています。」と回答。「私も最初は、会議で手術動画を見ても会話を聞いても何も分かりませんでした。しかし、その環境に身を置き続けることで、自然と重要なポイントが体に染み込んでいく。特に創業初期は役割が固定されておらず、先生へのインタビューの同席から薬事の検討まで、あらゆる球を素振りのように受け続けていました。」
また当時を振り返った時に、異なる業界であったとしてもビジネスである以上、何らかの要素は重なっていると感じたと述べた細見氏。ヘルステックと一括りにせず、自分の経験(細見氏の場合は、BtoBビジネスや公共セクターでの経験)と重なる部分を見つけることが大事であり、完璧な知識を身につけてからでないと挑戦できない、というのは思い込みかもしれないとも参加者に語りかけました。

医師から経営者になって感じたスタートアップ経営のリアルな面白さ
続いて、医師・研究者というキャリアから一転、スタートアップの経営者になった上野氏へ、そのキャリアの「面白さ」について質問が向けられました。
上野氏は「とてつもなく広い“裁量”と、自分たちが“道を作る”という感覚に面白さがある」と回答。
「創業したからこそ経験できたことは山ほどあります。当社であればIPOも経験して、そのプロセスを経験できたのは貴重ですが、やっぱり一番は事業面の裁量の広さが面白いところかなと思います」「IPO前後とか全く関係なく、本当に患者さんにとって何が足りてなくて、我々に何ができるのか、それ次第で0→1でパイプラインを作って、届けるところまでできる」
経営者として“事業を創るおもしろさ”を語る上野氏の言葉は、専門性を活かしつつ、より大きなインパクトを社会に与えたいと考える参加者に対して、キャリアの選択肢を増やすきっかけになったのではないでしょうか。

イベント全体を通じて、お二人からは「前例のない挑戦だからこそ、困難は絶えない。しかし、それ以上に得られるものがある」という力強いメッセージが伝えられました。
そして、企業の成長において最も重要なのは、強い“意志”を持つメンバーが集うこと。改めて「志」の重要性を感じることができる時間となりました。
Beyond Next Venturesでは、今後もこのようなイベントを開催予定です。
このレポートを読んで、デジタルヘルス領域の未来を創る一員になりたいと感じた方、トップランナーたちの「生の声」に触れてみたいと思った方はぜひ、以下のフォームからご連絡ください。
最新のイベント案内を受け取る
ニューズレターにご登録いただくと、弊社イベントのご案内をいち早くお受け取りいただけます。
キャリアについて相談する
HRメンバーとのキャリア面談も随時受け付けております。当該領域でのキャリアについて、情報交換やご相談をご希望の方はお気軽にご連絡ください。
▶キャリア面談の予約はこちら(https://calendar.app.google/gerzaQX4HFr8JnR28)