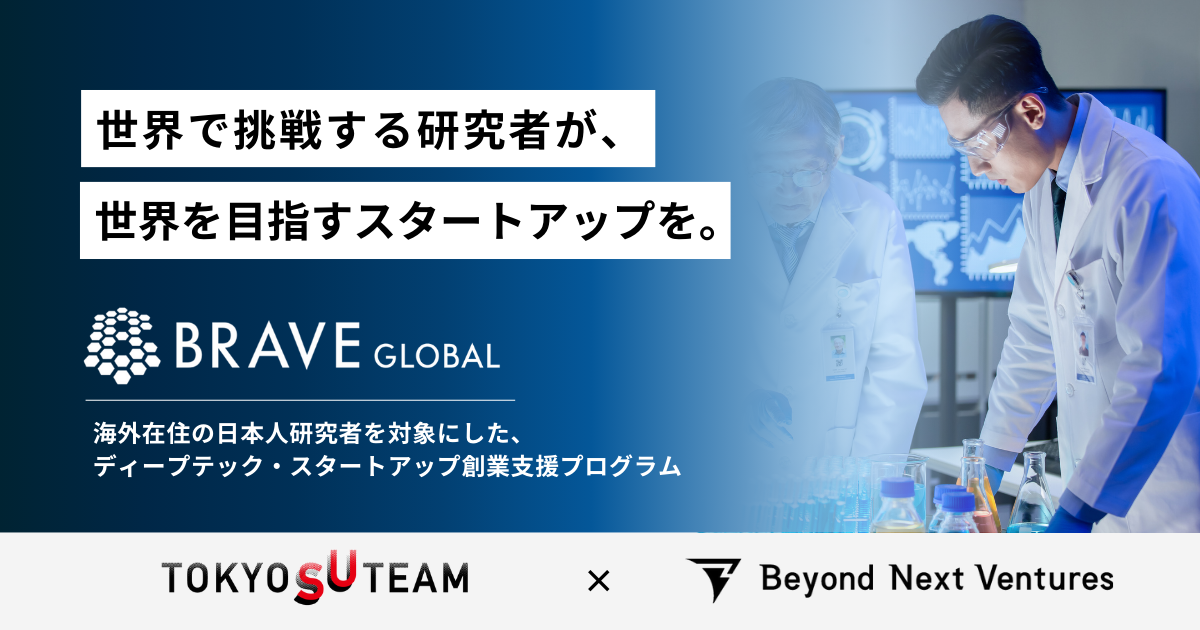2025年9月にシリーズAラウンドで10億円の資金調達を実施した株式会社さかなドリーム。東京海洋大学で培われた技術をもとに、「世界一旨い魚を創り、届ける」をミッションに掲げた水産スタートアップです。
同社が展開する「夢あじ」は、ミシュランの星付きレストランでも採用され、可能性を広げています。本記事では、創業の背景、Beyond Next Venturesとの出会い、技術のユニークさ、そしてシリーズA資金調達後の展望についてお届けします。
【Podcastでも配信中です!】
プロフィール

株式会社さかなドリーム 代表取締役CEO
細谷 俊一郎
丸紅にて穀物の流通全般および事業企画に従事した後、複数のベンチャー企業での事業開発やマネジメント、起業等の幅広い経験を積む。養殖業の持つポテンシャルに惹かれ、株式会社さかなドリームを共同創業。

Beyond Next Ventures株式会社 パートナー
有馬 暁澄
2017年4月丸紅入社。穀物本部にて生産から販売までのアグリ全般に携わる。また、アグリテック領域のスタートアップ投資チームを立ち上げる。2019年に当社に参画し、アグリ・フードテック領域のスタートアップへの出資・伴走支援に従事。2022年にパートナーに就任。農林水産省や大企業と連携し、産学官連携プロジェクト(農林水産省「知」の集積プログラム、「フードテック研究会/ゲノム編集WT」代表、スタートアップ総合支援事業「AgriFood SBIR」PMなど)にも取り組む。目標はアグリ・フード領域のGAFAを生み出すこと。慶應義塾大学理工学部生命情報学科卒業。
目次
「世界一旨い魚を創り、届ける」──異業種出身の創業者が選んだ水産スタートアップという道
有馬:シリーズAの資金調達が完了し、10億円という大きな金額を調達された、さかなドリームの細谷さんにお越しいただきました。シリーズAラウンドで二桁億円の調達を完了されるスタートアップが少ない中、今回の資金調達ラウンドを経て世の中の期待が高まっていると感じています。
本日はさかなドリーム社および細谷さんご自身についてもお話を伺いたいと思っています。ではさっそくですが、会社と細谷さんご自身の自己紹介をお願いします。
細谷氏:さかなドリームは、2023年7月に創業した水産系スタートアップです。私はもともと水産の研究やビジネスのバックグラウンドを持っていたわけではなく、最初のキャリアは総合商社の丸紅で、穀物部門に所属していました。その後いくつかの企業で経験を積んでいた頃、有馬さんから「そろそろ起業を考えませんか」と声をかけていただいたのが転機になりました。
その後、Beyond Next Venturesの「APOLLO」に参加し、数多くの研究者の方と出会う中で、東京海洋大学に在籍していた、そして今はさかなドリームの創業メンバーとなったCo-Founderの吉崎とCTO森田2名の研究チームとマッチングしました。
彼らが持つ魚の品種改良技術の話を聞いたときに、「これは間違いなく社会実装する価値がある」と直感し、創業を決意しました。
有馬:水産や農業など一次産業は技術を活かして効率化等に取り組むスタートアップが最近だと比較的多いと思うのですが、なぜ「魚の品種改良や養殖」だったのか、またなぜ「世界一旨い魚を創り、届ける」というミッションを掲げたのか、詳しく伺いたいです。
細谷氏:おっしゃる通り一次産業はまだまだ効率化の余地が大きく、技術によって解決できる課題も多い分野です。しかし私自身が、“効率化”というテーマにあまり情熱を持てなかったのが正直なところです。それよりも、“美味しいものを食べたときに人が幸せになる”という、極めてシンプルだけど普遍的な価値を提供することに強く惹かれました。
吉崎・森田からも技術を活かす方向性として、「ニッチでも本当に美味しい魚を広げる可能性」に関する考えを聞き、それが実現できるとおもしろいことができると率直に思い創業を決意しました。
その後、創業準備を進める過程で企業理念について有馬さんに相談したのですが、「企業理念は必ず創業前に決めたほうがいい」と背中を押していただいたことで、創業メンバー4人で議論を重ね、「世界一旨い魚を創り、届ける」という理念を定めました。
この言葉には、単に美味しい魚を“創る”だけでなく、それを“きちんと届ける”ところまで責任を持つという、我々の強い意志が込められています。
有馬:すごくカッコいいエピソードですね。創業前からその理念をメンバー全員で言語化できていて、本当に素晴らしいチームだと感じています。
市場と投資家を動かした、夢あじの“うまさ”と“ブランド力”
細谷氏:私たちの最初のプロダクトである「夢あじ」は、“カイワリ”という非常に珍しいアジ科の魚と、一般的によく知られるマアジを掛け合わせた新しい品種の魚です。
カイワリという魚は、吉崎と森田から話を聞くまで私自身も全く知らない魚だったのですが、豊洲市場の仲卸業者の方に話を伺うと一番好きな魚としてよく名前が挙がる、知る人ぞ知る魚だったのです。
この魚を養殖して展開できると面白いよね、という話から我々のプロジェクトが始まり、そこから品種改良に取り組み、2024年の年末頃から計3回、夢あじのテスト販売を開始。
ただ、テスト販売のタイミングは非常に悩みながら決定しました。その理由は資金調達を見据えていたため、テスト販売で結果を出す必要があったためです。よってタイミングについても有馬さんとも相談しながら検討を進めました。
“結果を出す”ことを考えた際に懸念点だったのは、一般的に養殖魚よりも天然魚の方がいいという先入観があると感じていた点です。実際に市場での評価も同様で、天然魚の方が評価される傾向でもありました。そのため高級レストラン等で養殖の魚が取り扱われることもまずない状況だったんです。
しかしテスト販売に踏み切ってみると、我々の夢あじ自身の品質や話題性によって、水産の卸業者の方々が夢あじを推してくださるようになりました。さらに予想外だったのは、夢あじをミシュランの星付きレストランや高級寿司店等がお客さまに提供する製品として購入していただくことができた結果に繋がったことです。
このようなハイレベルな飲食店で早い段階で夢あじを取り扱っていただけるとは想像していなかったので、非常に手応えを感じることができ、自信にも繋がった出来事でした。
有馬:まさにプロダクトマーケットフィットが成功した例ですね。この実績が、シリーズAでの資金調達にも直結しましたよね。世界一うまい魚を創っていけばマーケットに評価されることをより鮮明にイメージできた出来事でした。
何より4名の創業メンバーのみなさんの熱量がどんどん高まっていく様子を感じており、チーム力が非常に良くなっていっていると近くで見ていて感じていました。

異なる強みを持つ創業メンバーと組織の現在
細谷氏:ありがたいことに、「チームバランスがいいですね」と言っていただくことが増えてきました。実際、創業メンバーの4人それぞれが、異なる強みを持っていて、かつそれがうまく噛み合っていると私自身も感じています。
ビジネスサイドでは、私とCMOの石崎が主に経営とオペレーションを担っているのですが、異なる強みがありお互いに補完し合える関係性です。
研究サイドも同様で、Co-Founderの吉崎と、CTO森田もお互いの強みを活かしてくれています。実はこの2人、師弟関係でもあるのですが森田は大手水産系企業での実装経験を有しているため、“研究開発”と“現場実装”のバランスが取れており、研究から社会実装までをつなぐプロセスが自然にできているんです。
有馬:確かに、最初からこの布陣を狙って集めたようなバランスですよね。特に吉崎先生のような世界トップレベルの魚類研究者と、その技術を世に出そうとする起業家がチームを組めている点が素晴らしいと思います。
細谷氏:少数精鋭ながら、自分たちの魚に誇りと愛情を持って日々取り組んでくれていると実感しています。なぜなら、「夢あじ」という名前で世に出している以上、これは誰が携わってきた魚なのかが明確だからです。現場のメンバーたちも手触り感を持って仕事に取り組めるため自分事化しやすいため、熱意を持って仕事に取り組んでくれているように感じます。
有馬:これは本当に大事なポイントで、特に今のさかなドリームのステージだからこそ自分自身の力も試しやすいタイミングなのかもしれないですね。
現在の組織の状況についてお伺いできますか。
細谷氏:現在の社員数は創業メンバーを除いておおよそ15名ほどです。魚の飼育や研究をしているメンバーが割合としては多く、ビジネスサイドで仕事をしているメンバーも若干名います。
特に研究や養殖の業務に携わっているメンバーは本当に魚が好きなメンバーが多く、海の仕事が好きで当社を見つけてくれたメンバーもいました。しかし好きだけでは成り立たないのがこの仕事で、どこまでいっても生き物を取り扱う仕事のため思い通りにいかないことも多くあるのですが、そこに向き合う強い精神力や忍耐力が必要になります。
有馬:たしかに他の企業ではあまり伺わないお話ですね。社内でのコミュニケーションはいかがでしょうか。
細谷氏:年に1回、社内でキックオフは開催しているのですが、生き物を扱う商売のため「今は目が離せない」や、「この時期にしかいない珍しい魚をとある島に獲りに行かないといけない」など様々な事情が重なってオンラインで参加してもらうこともしばしば起きています。
よって飲み会等、業務外でのコミュニケーションはあまり多くないのですが、「魚が好き」という絶対的な共通点があるので、コミュニケーションの量は多い会社だと思います。私自身も魚の世話をする場面があるのですが、メンバーとコミュニケーションを取って楽しみながらやっています。
有馬:経営陣との距離が非常に近い環境ですね。ちなみに今後、組織として強化したい点はどのようなことでしょうか。
細谷氏:これまでと変わらず、当社は研究が元となっている会社のため、研究や飼育の技術を活かして活躍していただける方の力はこれまで同様に強化していかないといけません。
あと今回、非常に大きな規模の資金調達が実現できたので、設備投資にも力をいれたいと思っています。よってビジネスサイドを強化し、事業戦略を練り会社の成長にもしっかり繋げていきたいですね。
このように様々な取り組みを行っているフェーズのため、会社の成長とともにご自身の成長も実感していただける環境だと思っています。もしご自身の力を試したいと考えていらっしゃる方がいらっしゃいましたらぜひ一度お話する機会をいただきたいですね。
世界へ広がる“夢あじ”──事業会社との連携とその先に描くビジョン
有馬:順調にシリーズAまで進めてこられて、今後のスケールアップがいよいよ本格化していく段階に差し掛かりましたが、次のフェーズでは事業会社との連携がより重要になってくるのではないかと思っています。
細谷氏:おっしゃる通りです。我々は“食”の領域で事業を展開しているので、“食”に関連するビジネスを展開している企業の方々から関心を持っていただけると嬉しいですし、実は既にお声がけもいただいています。実際にあったご相談は、新規事業で“陸上養殖”に関するもので、ご相談していただいた件数も比較的多いと感じています。
今のところ当社は陸上養殖に向けた具体的な活動はしていないのですが、今後、陸上養殖にも挑戦する可能性もあるので、魚関連で新しいことをしようと考えられた際に、当社の名前が挙がってくるような状態になるとすごく嬉しいと感じます。
陸上養殖に取り組んでいない理由は、夢あじは海で養殖するのが向いている魚だと考えているためです。一方で新しい魚の開発を考えた際に、陸上養殖の方が相性がいいと感じている魚もあるので様々な可能性を探っていきたいです。
有馬:たしかに一次産業系は新規事業として取り掛かりやすい分野ではありますし、自社が持つ特徴とシナジーを生み出しやすい部分ではありますよね。
細谷氏:あとこれは私とCMO石崎の覚悟でもあるのですが、共同創業者である吉崎は、世界的にみてもトップクラスの魚類研究者で、彼が開発した技術もとても注目されています。私は縁あってその技術の社会実装を任せてもらった立場なので、当社の事業を世界に羽ばたかせていく責任があると思っています。
ちなみに養殖の市場は世界で25兆円ほどで、日本では3,000億円程度なのですが、日本の養殖技術は世界でトップクラスです。なぜなら日本の魚は美味しい、だから日本でやる理由があると思っています。
その上で、我々が持つユニークな技術で価値ある魚を創り出していく──これは十分にグローバルで勝負できるテーマだと思っています。
とはいえ、まだまだ私たちはスタートラインに立ったばかりです。だからこそ、今後はより多様な企業や人材と手を取り合いながら、社会実装を進めていくフェーズに入ったと思っています。
これから養殖や水産の領域で新しい挑戦をしたいと考えている企業の皆様にとって、私たちが最初に相談いただけるような存在になれたら嬉しいですね。 また、チームとしてもアーリーフェーズだからこそ、裁量を持って働きたい方、新しい市場を一緒に切り拓きたい方とぜひご一緒できればと思っています。
有馬:細谷さん、本日はカッコいい創業ストーリーから、夢あじの可能性、そして資金調達についてお話いただきありがとうございました。
▽さかなドリーム社のnoteはこちら
世界一旨い魚を創り、届けるための「これまで」と「これから」 - さかなドリームの未来の仲間へのメッセージ|CEO 細谷俊一郎
https://note.com/sakanadream/n/nddc307f5c7bc
▽さかなドリーム社の採用情報はこちら
https://sakana-dream.com/recruit