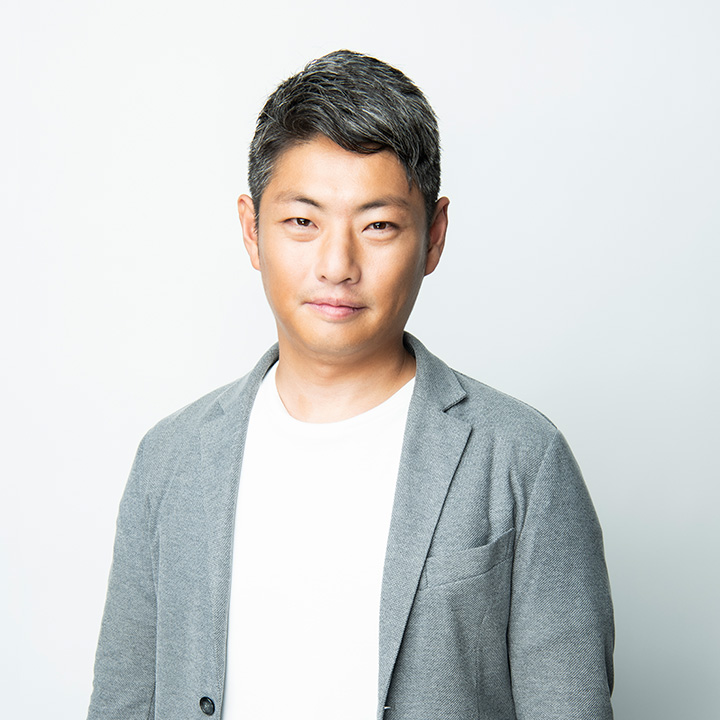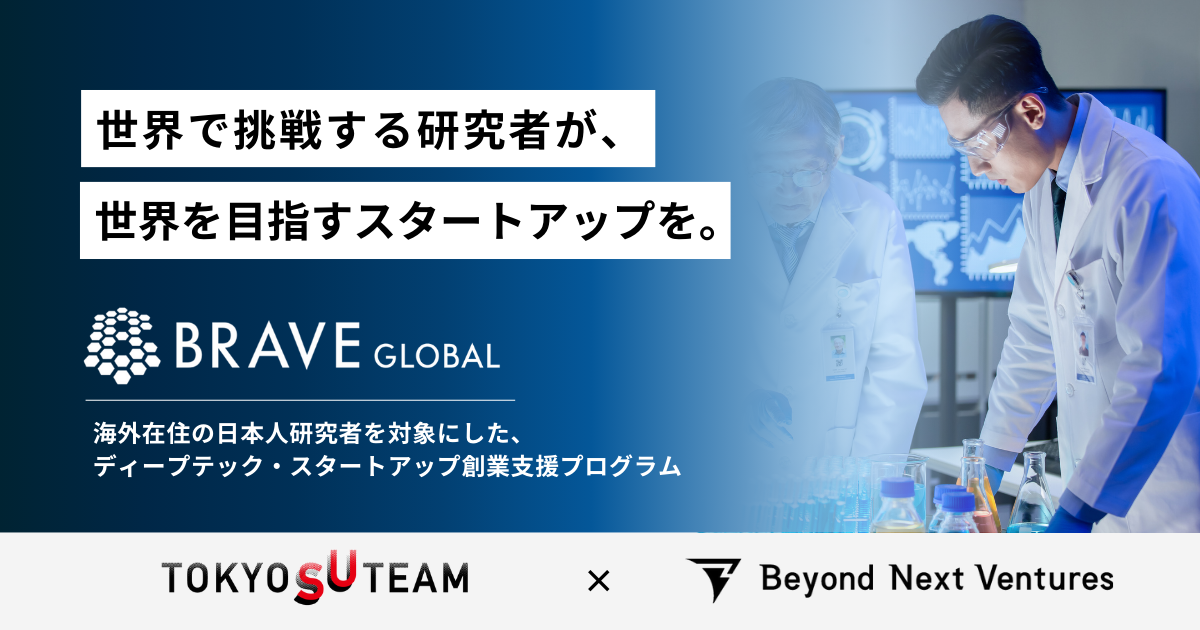“薬事”業務は事業開発の一部──日本初のデジタル治療アプリの薬事承認を経験した担当者と考えるDTx・SaMDのこれから
DTx(デジタルセラピューティクス)やSaMD(Software as a Medical Device)は、医療の未来を変える可能性を秘めた分野です。しかし日本ではまだまだ実例が少なく、開発や薬事承認についてノウハウが少ない状況となっています。
今回は、CureAppにて日本初のDTx薬事承認を実現した武田氏とBeyond Next Ventures パートナー橋爪が、開発現場でのリアルな課題や、薬事を乗り越えるための考え方、そして今後の展望について対談しました。
プロフィール
株式会社Software Regulation 代表取締役
武田 瑛司 氏
日本初となる治療用アプリである株式会社CureAppで禁煙と高血圧の治療用アプリの薬事申請を担当した経験を持つ。CureApp退職後、プログラム医療機器の薬事申請を支援する会社を設立し、治療用アプリだけではなく、AI/MLの診断用プログラムなど、SaMD開発を行う企業において、国内外の薬事業務全般を支援。
Beyond Next Ventures株式会社 パートナー
橋爪 克弥
2010年ジャフコ(現ジャフコグループ)入社。産学連携投資グループリーダー、JST START代表事業プロモーターを歴任し、約10年間一貫して大学発ベンチャーへの出資に従事。2020年に当社に参画し、医療機器・デジタルヘルス領域のスタートアップへの出資を手掛ける。2021年8月に執行役員に就任。投資部門のリーダーを務めるとともに、出資先企業のコミュニティ運営を統括。主な投資実績はマイクロ波化学(IPO)、Biomedical Solutions(M&A)、Bolt Medical(M&A)等。サーフィンが趣味、湘南在住。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了。
現在の仕事に繋がるキャリア
橋爪:まずは武田さんのキャリアについて伺いたいのですが、CureAppに入社する前はどんな経験をされてきたのでしょうか?
武田氏:もともと大手の製薬会社で品質や信用保証、薬事関連の業務に携わっていました。人数が少ない部署で仕事をしていたため「何とか効率化できないか」と思い、独学でプログラミングも学んだりしていました。そんな中で日本初のデジタル治療アプリを目指すCureAppの存在を知り、これは挑戦してみたいと思い実際に薬事承認まで経験をしました。そして現在はSoftware Regulationの代表として薬事関連のアドバイザーとなり様々な企業のお手伝いをしています。
橋爪:では“デジタル×薬事”という仕事は、CureAppに入社してから初めて挑戦されたんですね。CureAppでの経験についてもう少しお伺いしたいのですが、実際にどんな苦労があったのかお聞かせいただけますか。
武田氏:私がCureAppに入社をしたタイミングがコロナ禍の真っ只中だったため、入社後のオンボーディングをするにも密なコミュニケーションが難しい状態で、「いきなり現場投入」という状況でした 。今思うとなかなかにタフな環境で、PMDA[1]とのやり取りやドキュメント整備も、自分でやりながら覚えていったという感じでした。一方で今振り返ると、短期間でいろんなことが経験できたのですごく貴重な経験だったと思います。
薬事業務は“守り”から“攻め”へ
橋爪:DTxの薬事対応って、既存の医療機器とは少し違う難しさがありますよね。
武田氏:そうですね。大手企業にいた頃の薬事業務は“守り”のイメージが強かったのですが、CureAppで対応をしていた当時を思い返すと、比較的企業側の主張を受け入れてもらいやすかったように感じます。
橋爪:CureAppの場合は日本で初めての承認ということもあり、PMDA側も一緒に考えながら進めていくというスタンスだったんですかね。
武田氏:そうだと思います。PMDAと対話する前は、社内のメンバーも厳しいことを言われるのではないかとプレッシャーを感じあれこれ準備をして臨んだのですが、実際は想像以上に柔軟に私たちの考えを受け入れてくれる場面が多くありました。驚きとともにもっと活発にコミュニケーションを取るべきだと感じた経験から、今もDTxやSaMDの承認はアグレッシブにいこうという気持ちでいます。
PMDAとのやり取りについて極端に表現すると、積極的に提案することでプロジェクトが前進する といった感覚で、それがいいのか悪いのかを判断するのは当局側の仕事だと思うことが大事だと思います。よって企業側で「この点は言わないでおこう」といった手前での判断は不要ですしもったいないので“攻め”のスタンスで臨んでいただきたいです。
大手企業とスタートアップ、それぞれにおける“薬事”の違い
加藤氏:自社の意見を述べることに関連するのですが、私はスタートアップにおける薬事業務は事業開発の一部だと思っています。大手企業ではそれぞれが別の部署で、薬事はどちらかというとコンプライアンスを見守るような立場という扱いをされがちですが、スタートアップでは事業開発寄りな立場で「どこまで広げるか」まで一緒に考えます。
橋爪:確かにそうですね。一般的に薬事業務は守りっぽい印象がありますが、最近のDTxやSaMD、AI医療機器といった新しい機器などについては事業開発のような動きをしている印象がありますよね。
武田氏:スタートアップにおける薬事は事業としてコストを下げスピードを維持しつつ、可能な限り多くの患者さんに使ってもらう、といった要件を満たせるように、戦略を立てて実行する役割を担っていると思っています。過去に私が在籍していた大手企業の薬事業務は、製品のメンテナンス等をコントロールしている役割だった印象なので、一言で薬事といっても全然異なります。
この違いは採用活動にも影響するのでぜひお伝えしたいです。恐らくスタートアップ側からすると、何も分からない状況のため薬事業務の経験者の方に入社して欲しいと思っていると思うのですが、持っている経験値とニーズが合致ないケースが起きうるのです。
採用される側(入社する立場)の視点で言えば、規制に関する知識や経験などを活かすことが求められるというイメージですが、採用する側は、規制に関する知識や経験などに加えて、事業の全体像を理解した上で事業計画に合わせた申請計画(プロジェクトマネジメント)、可能な限り多くの患者さんに使用してもらえるような資料作成(交渉能力)など、事業計画における薬事というマイルストーンを一定の基準をもって達成することを求められるイメージです。薬事という専門性を活かして、ランウェイの短いスタートアップで薬事取得に関するあらゆるタスクを担うことに必要だと考えます。
橋爪:たしかにそうですね。スタートアップという組織において、“誰がやるのか”という観点はすごく重要だと思います。
他の観点で薬事においてスタートアップが陥りやすいポイントはありますか?
武田氏:先ほどの話に紐づくのですが、薬事承認の際に担当の方は何事もなくスムーズに進めたい気持ちがあると思います。そうなるとPMDAや当局の方と議論になるような揉め事を避けたいと思い、保守的な行動取るようにな心理状態になるのではないでしょうか。
しかし実際に薬事担当の方に求められることは、タイムラインを守りつつギリギリのリソースで事業戦略を見据えた薬事承認 を取りきることです。これが実現できるようにプロジェクトをリードできるような人がスタートアップでは求められる。このバランスが難しいのではないかと思います。
薬事承認は“対話”で動く──主張と交渉のリアル
武田氏:PMDAへの相談方法[2]は無料の相談と、対面助言という有料の2種類があります。有料のものはPMDAによって議事録が作成されるので、どのような議論をしているのか機会があれば一度見てみてください。
議事録を読んでいくと、“異論ない”や“受け入れられない”、“企業の主張は理解できる”といったキーワードが出てきます。“異論ない”は保守的に進んでいる、“企業の主張は理解できる”が出ればチャレンジの余地がありうまくいったという感覚です。
このように並ぶと“異論ない”が一番いい回答に感じますが、保守的に設定すればするほど“異論ない”という回答にはなるので、それでいいのかは考えた方がいいと思います。例え難しい部分があったとしても企業としての考えや、やりたいことを主張して欲しいです。
“企業の主張は理解できる”は“異論ない”の回答ではないため、例えば二重盲検試験の実施を求められることもあるかもしれません。しかしそこを勝ち抜くための治験デザインが薬事担当には必要になります。その結果、条件付きだったとしてもポジティブな回答を得ることができればある意味勝ちだと思います。
橋爪:先ほどもお話されていたちゃんと主張することが大事だということですね。むしろ主張をしないと保守的すぎるような印象を受けました。
武田氏:その通りで、掘り下げることができる幅はあるのに自分たちでそこを制限してしまうのはもったいないです。もちろんそれで治験に勝ち、その後の疑義も出ないのであれば異論ないで進んだ方が当然いいに決まってますが、DTxにおいてはなかなか難しい試験という性質もあると思います。その場合においては、“勝てる治験デザイン”を組むことが何に関しても優先されると思うのでチャレンジして欲しいと思います。
橋爪:今の話を踏まえて、開発の初期段階から薬事を見据えて意識すべき点はありますか。
武田氏:デジタル医療機器の中でもいくつかパターンがあるのですが、型が決まりつつある印象を持っています。よって製品の特性を踏まえてどの方法が最適かを考える必要があると思っています。
たとえば、治療用では非盲検の試験や、探索試験で“シャム効果”を測ることが求められる傾向にあります。診断用であれば、AI単体の性能評価や読影試験など、いくつかのパターンがあり、それぞれコストや承認までのスピードに影響します。AI単体の評価であればコストパフォーマンスは良いですが、PMDAとの議論が増える側面も。一方、読影試験は医師の協力が必要となり費用がかかる…。
よって製品の特性に応じて「勝てる型」を早期に見極めておくことが、後々の戦略の幅を広げることにつながると考えています。
橋爪:なるほど。その型に合わせた治験デザインを前提に開発を進めるということですね。
武田氏:理想的なのはその方法だと思います。もう少し具体的に話をすると、探索試験で通常診療との比較や非盲検を取り入れる場合も、背景説明がきちんとされていればPMDAにも理解されます。そのためには、事前にシャム群などとの比較が難しい理由を示すデータを出しておく必要がある。そこまでの流れを早い段階で作っておくことで、PMDAも納得できる治験デザインが組めるわけです。
最短で進めたいなら、単群の探索試験でリスクを取りつつもスピード優先で進む方法もあります。実際には、ADHD治療アプリのように慎重に検証を重ねたことが見受けられる例もありますし、解決したい課題、製品、会社の状況 によって取り得る選択肢はさまざまです。
探索試験の段階でPMDAが求める評価を意識することで、その後の治験設計も柔軟に進められます。「通常診療との比較」や「非盲検でもOK」という流れは、背景説明がしっかりしていれば通るんです。その布石をどれだけ早く打てるかが、薬事の成功を左右します。
海外薬事のリアルと日本との違い
橋爪:話を変えて、海外展開についてお伺いできればと思います。武田さんも海外展開のプロジェクトに携わられていると思うのですがその際に押さえておくべきポイントなどありますか。
武田氏:海外展開について私自身もまだ手探りな状況なのですが、苦労されている企業が多い印象を持っています。
その中で感じていることとしては、FDA[3]は基本的にPMDAとアプローチは似てます。PMDAの全般相談や対面助言に当たるものに早めに着手し、回答するのが大事だと思います。
ただし日本で通った治験設計がそのまま使えるとは限らないです。たとえばポリープ検出AIでは、日本は単体性能でOKでも、FDAでは600人以上の治験を求められました。
橋爪:そうゆう意味でも早めにプレサブ(Pre-Sub)を行い、コミュニケーションを取っていくことも大事ということですかね。
武田氏:そうですね、結局はそこに行き着くと思います。あとはFDAについてはFDAに強い“現地のコンサル”の存在も重要になります。
DTx・SaMD薬事における2つの注目トレンド
橋爪:海外のお話を伺いましたが、日本においても規制環境の変化など様々な動きが起きていると思います。最近の薬事について武田さんが注目されている事例やポイントについてお伺いさせてください。
武田氏:ではトレンドについて2点お話させていただきます。
1つ目は診断用のモニタリング型のSaMDが新たに承認されるトレンドが加速するのではないかと思っています。たとえば心疾患の患者さんについてこれまで通院をして診察を受けていますが、遠隔でのモニタリングでも通院と同等の治療効果が出ている結果が出て承認されている事例などが出ています。
ウェアラブル端末を人と融合させて製品開発を進めている会社も出てきているので、モニタリングの文脈でいろんな疾患に対するデジタル治療機器が今後も出てくるだろうと想像しています。
橋爪:治療用アプリやAI診察などはこれまでも出てきていますが、モニタリングは新しく登場したカテゴリという印象ですね。
武田氏:個人的には治療に近いカテゴリの印象ですが、モニタリングというものがPMDAの中でもパッケージとして出ており、これから同様の製品が世の中に出てくるそんなステージに来ているのだと思います。
2つ目は非侵襲診断[4]。診断をしたくない人を診断のステージに持ってくるような製品も複数出てきている印象です。
橋爪:患者さん身体への負担が従来だと高く避けがちな検査などについて、受けないことで疾患の発見が遅れてしまことをソフトウェアやAIの力で侵襲性を減らすということですよね。
武田氏:そうですね、下剤不要の大腸診断や、脳脊髄液を採取せずに病気を判別するAIなど、患者負担を軽減する製品が出てきました。このような前処置をなくして同じ程度の精度を出すことができる製品が出てきているので、やはりデジタルやAIの力はすごいですし、強い力を持っていると感じています。
CTやMRIのような既存の仕組みでも同様で、取得したデータをAIの力を使うと精度の高い検査をすることができます。高い技術があってこそだとは思うのですが、このような製品の開発が進み、2-3年後くらいにはそのような製品が承認品目として出てくるのではないかと思っています。
あとトレンドではないのですが、今後出てくるものとしてリスク予測が挙げられると考えています。これまでお話したモニタリングと非侵襲診断を治療の時系列で並べると、モニタリングは治療後の状況確認、そして非侵襲診断は診断のステージを指しているのですが、そのさらに1つ前のリスクの予測ができるような製品です。
橋爪:確かに時系列については似たような感覚を私も持っています。2020年頃からAIの医療機器製品が出ていますが、診断成績を底上げするところから始まり、今は診断フローの手前からモニタリングまで幅広い時系列的に横が広がったのがある意味、第2世代じゃないですが特徴的な点だと思っています。
リスク予測について、たとえば心臓や脳、あと癌のような重篤な疾患について、より早期の発見が求められるような疾患がそのような相性がいいんでしょうか。
武田氏:まさにそのような疾患が相性がいいと思いますし、すでに承認を取っている事例も出てきています。
そのため直近で既存のCTやMRI、心電図などの既存のデータがある程度あるものに関しては、さらに微細な変化を読み取ることによって解析精度を高めるような製品がここ3-5年ほどで出てくるのではないかと思ってます。一方でデータに依存しない、全く新しい情報をベースに構築するのはそもそもデータがないと思うので、そこは少しもう少し長い話だとも思いますね。
先ほどお話のあった、診断成績を底上げする点については、様々な分野で複数の製品が出てきているのでまさにご指摘の通りだと思います。次はそこからさらに、サポートが難しいことを対応することや、積極的にしなくていい検査を受けずに済むようにするといったことが実現できる製品開発が動いてるのだと思っています。
薬事パーソンに求められる姿勢
橋爪:最後に今後、SaMDやDTx等の薬事担当に携わる方に向けてメッセージをお願いします。
武田氏:やはり知見のシェアですね。日本では成功事例も失敗事例もなかなか外に出にくい。でも、それがイノベーションを阻んでいる部分もあると思っています。成功も失敗も含めて語れる場をつくることが、業界全体を育てるんじゃないかと思っているのでそのような取り組みができる場があると嬉しいですね。
橋爪:その意味では、我々がやっている勉強会[5]もそうした場に近いかもしれませんね。
武田氏:はい、具体的な実例ベースで議論できるあの場は本当に貴重です。薬事は孤独になりがちなので、横のつながりがあるだけでも大きな支えになります。一緒に頑張っていきましょう。
橋爪:武田さん、本日はありがとうございました!
[1] PMDA:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
[2] PMDAへの相談方法:医療機器審査部が実施している相談について
[3] FDA:米国食品医薬品局
[4] 非侵襲診断:身体に負担をかけず、生体を傷つけない方法で病気や体の状態を調べる診断方法
[5] 勉強会:SaMDビジネスセミナー (第3回) 実例で学ぶSaMD保険戦略最前線|治療用アプリからAI診断まで
【Podcastでも好評配信中です!】