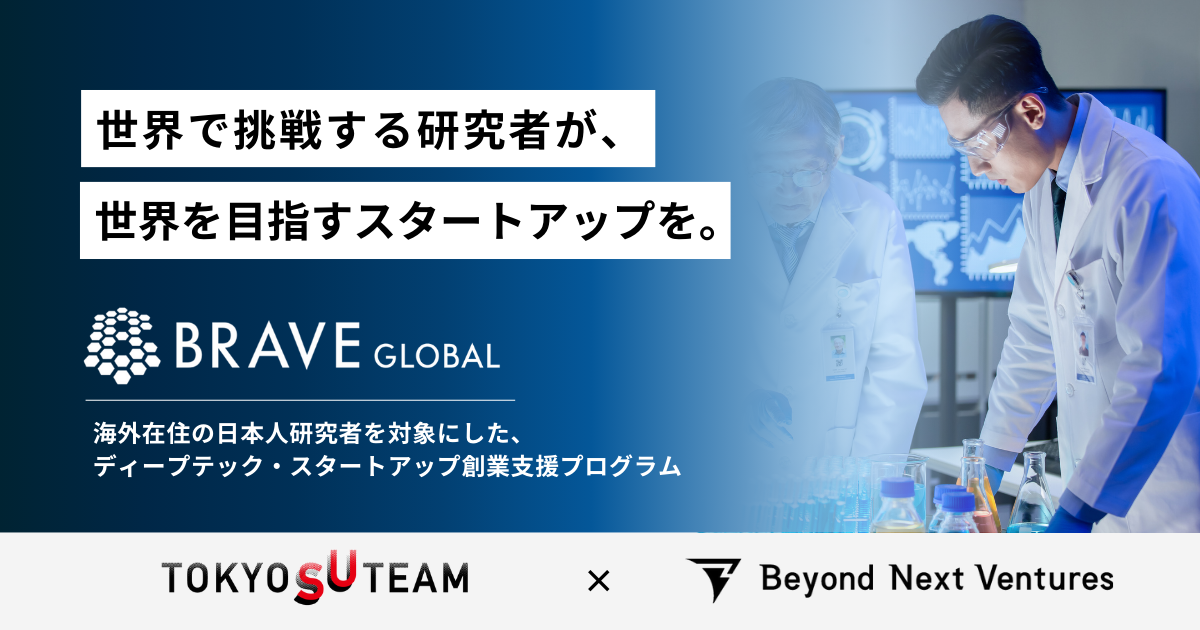2025年3月にアメリカで開催された世界最大級の食品展示会「Natural Products Expo West」に参加してきました。今回は、現地で見えた最新トレンドを整理しつつ、そこから得られた示唆を共有したいと思います。
目次
「Natural Products Expo West 2025」
Natural Products Expo West 2025
- 開催時期:2025年3月4日~3月7日
- 開催地:アナハイム / アメリカ
- 会場:Anaheim Convention Center
- 出展対象品目:ナチュラル・オーガニック食品、健康食品、機能性食品、サプリメント、ビューティー&ホーム用品等
- 公式ウェブサイト:https://www.expowest.com/en/home.html
中国企業ブースとキノコ系スタートアップが大幅減少
有馬:今年も2〜3万人の規模の来場者数で非常に盛況で、個人的にも密度の濃い時間を過ごしてきました。しかし昨年と比較すると中国企業のブースが大幅に減っていたように感じます。一方で、そのほかのアジア系や諸外国のスタートアップがやや増加した印象を受けました。
中国の企業が減っていると感じた理由は、昨年は餃子や小籠包といった中国ならではの食品のブースが非常に多かったのですが、明らかにその数が減っていたためです。その背景にはアメリカの政権や、中国国内のスタートアップに関する事情が影響しているのではないかと想像しています。
一見ネガティブにも見える動向ですが、日本企業の海外進出にとっては追い風になり得る動きでもあり、今後の動向を注視したいです。
他には、前回のレポートで取り上げたキノコ系のスタートアップは明らかに数が減少していました。真相は分からないですが、実際に私たちも昨年試食した際にはそこまで味の魅力を感じられなかったので、消費者の支持を得られなかったのではないかと思います。
一方でプラントベースフードのクオリティは飛躍的に向上しており、明らかに美味しくなっていました。
プラントベースフードは転換期を迎えている
プラントベースフードのクオリティが飛躍的に向上したことは業界的にいい傾向ではありつつ、日本にとっては脅威になると感じています。その理由は、これまで日本は、諸外国と比較した際に食文化が優れている影響から味へのこだわりが強く、それに伴いプロダクトの完成度が高くなるため優位性を保てていました。
しかし今回、米Impossible Foodsを中心に他のプラントベースのプロダクトを試食したところ、明らかに味が改善していました。今後もこのペースで進化を続けると、日本の競争優位性が担保されにくくなる未来を想像してしまうレベルでの改良だったと感じています。そのため、このプラントベースフードの領域で海外進出を考えている日本の企業は、早い段階で挑戦することに価値があると感じています。
また、個人的には今回さまざまなプラントベースフードの試食を通じて、今後の食文化の進化に期待を持ちました。というのも、これまでプラントベースフードは美味しいと感じる製品が少ない傾向にあり、ベジタリアンやビーガン以外の一般消費者は敬遠しがちでした。しかし全体的に味がかなり改良されて、一般消費者の方も手に取りやすくなってきたと感じています。
そもそも植物性の原料で作られている食品を中心とした食事は、多くの研究などでも健康へのメリットが提示されています。今回の視察を通じて、健康食品の選択肢のひとつに、美味しいプラントベースフードが当たり前に入ってくる未来も遠くない、そのように感じましたね。


「機能性食品」が増加。海藻人気も顕著に

昨年はドリンク類のブースが目立っていた印象だったのですが、今年はフード系のブースの方が目立っていて、中でも「機能性」に関するプロダクトは数も明らかに増えていました。
グルテンフリーやGABA、DHAが豊富なプロダクトや脳がすっきりする効果を謳うものなど、様々な種類がありました。プロダクトの種類についてもグミなど手軽に食べることができるものもあり、今後もトレンドが続きそうです。
他には、海藻系のスタートアップも増えていましたね。海藻やこんにゃくを使ったお寿司やドリンクなどの商品が並んでいたのも印象的でした。当社が出資しているAqua Theonもその一社で、今年も4回目のブース出展をされていたのですが、これまで見かけなかった企業も多数いらっしゃって、全体的に海藻トレンドの波が高まっている様子が見れました。

Natural Products Expo Westはトレンドをいち早く知れる場
世界各国のバイヤーがここに集まってトレンドを感知しているのは明らかです。最新のフードテックの潮流を知りたければ参加すべきですし、アメリカへの進出を考えている企業は展示も含めて検討し、バイヤーと接点を持つことをお勧めします。
また、例年参加者の顔ぶれは固まってきていて、コミュニティが形成されて同窓会のような雰囲気もあります。このコミュニティに加わることも非常に重要だと思います。
先ほどプラントベースフードの味の進化に触れましたが、最近登場したプロダクトの中には、まだ改善の余地が残るものも多い印象で、日本の勝ち筋は残っていると思います。日本企業は早めにマーケティング戦略を立てトレンドをキャッチし、海外進出を目指してほしいです。
特に、日本の発酵技術力は非常に高く、例えば「麹」は海外でも「koji」と呼ばれていたり、抹茶のブースは昨年と変わらずたくさんありました。日本ならではのよさを組み合わせることによって、世界とも渡り合うことができる余地はまだまだたくさんあると感じています。