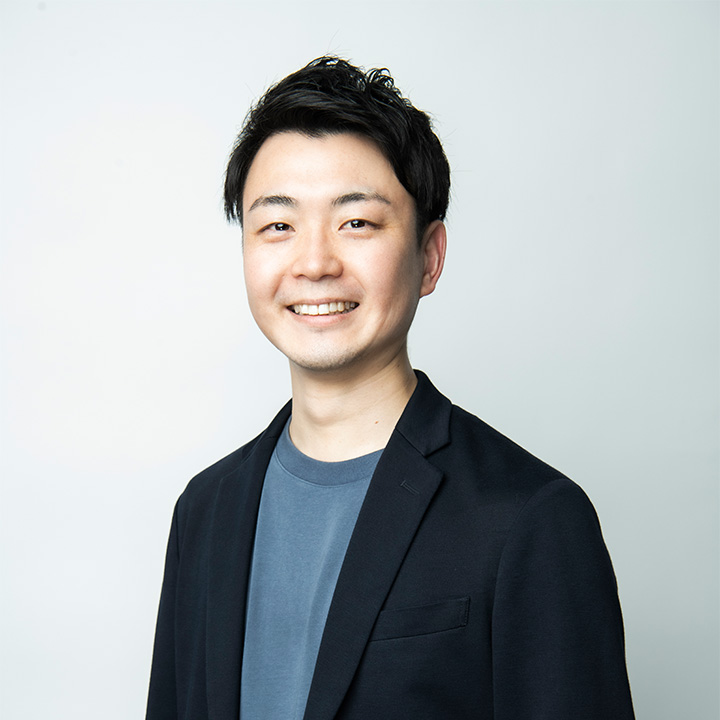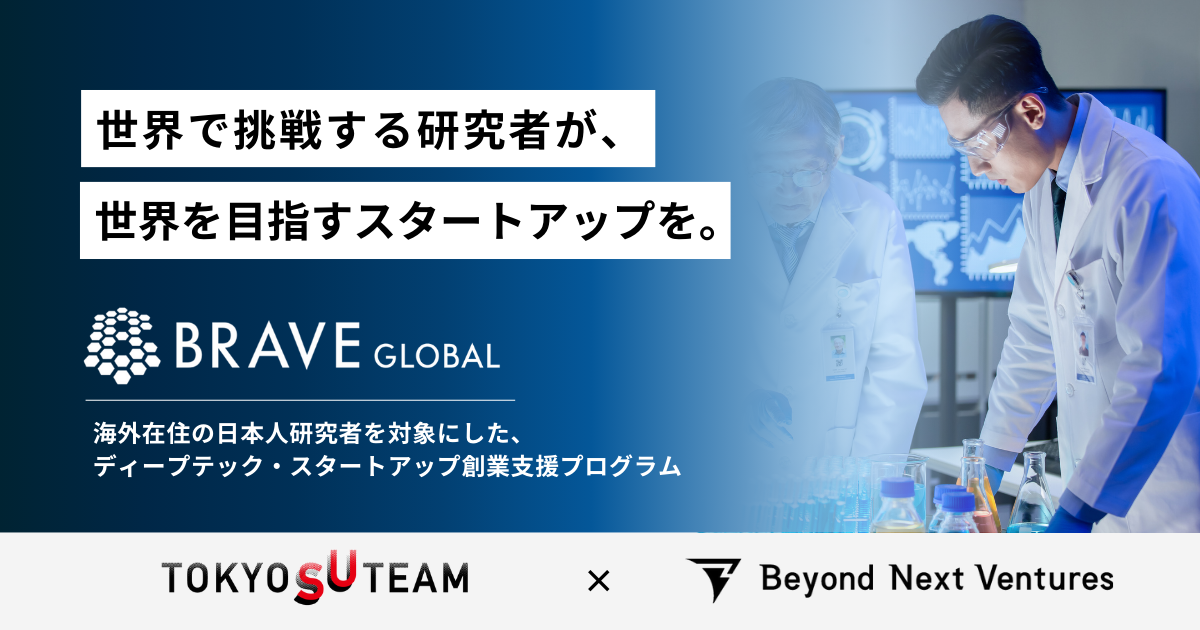Beyond Next Venturesが共催として参画した、日本初のディープテックに特化した国際カンファレンスである「TECHNIUM Global Conference」。5月7日・8日に開催された本カンファレンスには、日本のディープテックスタートアップを牽引するトッププレイヤーたちが集結し、多数のセッションが行われました。
カンファレンスは完全招待制で開催され、多くの反響をいただいております。当日ご来場が叶わなかった方にも内容をご紹介したくセッションレポートを公開いたします。
その中から本レポートでは、「未来を切り拓いた起業家たち—ディープテックスタートアップ上場のリアルストーリー」をご紹介します。
Session Title:
未来を切り拓いた起業家たち—ディープテックスタートアップ上場のリアルストーリー powered by Beyond Next Ventures
モデレーター
粟生 万琴(株式会社LEO 代表取締役CEO)
登壇者
- 出雲 充(株式会社ユーグレナ 代表取締役社長)
- 袴田 武史(株式会社ispace 代表取締役CEO & Founder)
- 福田 惠一(Heartseed株式会社 代表取締役社長)
セッションの冒頭、口火を切ったのはユーグレナの出雲充氏。ユーグレナはミドリムシを活用した食品、化粧品などを手掛け、バイオ燃料にも取り組んでいる。出雲氏は、岸田内閣が掲げたスタートアップ育成5か年計画が折り返し地点に立っていることに言及。「ベンチャーの裾野を10倍に広げ、ユニコーン創出でスタートアップの『頂点』を10倍にし、リスクマネーの供給額を10兆円するというこの計画。残りの期間でどうやって日本をスタートアップ大国にしていくのか、今日は議論したい」と語った。

ispaceの袴田武史氏は、アジア初の月面着陸を民間人で実現させるというミッションに取り組む。福田惠一氏が代表を務めるHeartseedは慶應義塾大学発ベンチャーで、心不全を心臓移植ではなく、iPS細胞から作った心筋細胞を移植するという再生医療の開発に取り組んできた。
またモデレーターの粟生万琴氏もAIのスタートアップを10年前に創業し、IPOを経験した経営者の1人。現在は名古屋大学でスタートアップ支援をしており、日本におけるエコシステム創出についても触れるセッションとなった。
とにかく社会実装したかった
粟生氏は、「研究者の道から、なぜ起業に?」という質問を最初に投げかけた。

「とにかく社会実装をしたかった」と語るのは出雲氏。近年、東大生でも官僚になるのではなく、起業を選ぶ人が増えてきたとした上で「いい研究をして、それを社会実装するためにスタートアップを増やす。政府の5か年計画でいうように、その数を10倍にしていけば、日本、そして世界の社会課題解決につながるはずだ」と力強く述べた。
福田氏は「自分が20代の時には、拡張型心筋症は心臓移植以外では治療が不可能だった。自分と同年代でこの病気を患っている患者さんを担当して、何も治療法がないという現実に直面したときに、治療方法を科学の力で開発しなければならないと強く思った」ことがきっかけだったという。強い決意で2015年に会社を立ち上げたが、大学関係者の目線は冷ややかなものだった。当時の大学では「教授がベンチャーなんか作ってどうするんだ。ちゃんと研究はやっているのか」という見方が主流だったからだ。

長らく日本の大学発スタートアップは逆風にあったが、近年の変化について、出雲氏が解説を加えた。「日本の大学発スタートアップの数は4000社を超える数になり、東大は400社超、慶應や京大は300社弱。エコシステムの醸成は実例が出てきたから、ここからは地方の大学や国立研究開発法人などに、どんどん拡大していくステージだ」(出雲氏)。
袴田氏は大学・大学院で航空宇宙工学を専攻。「お二人と違って自分は研究者ではない」としながらも、宇宙の社会実装という点では、大学院時代にすでに関心が芽生えていたという。大学院卒業後、一旦はコンサルティング会社に就職したものの、宇宙への思いが途切れることはなかった。月面探査レース“Google Lunar XPRIZE(GLXP)”への誘いを受けて、宇宙の社会実装という分野へと踏み出していった。
上場までの道のり~ハードシングス~
粟生氏は次のテーマとして「上場までのハードシングス」を提起した。福田氏は、先輩起業家が後輩起業家に、資金調達やIRなど上場までの道のりを伝授する大学内の仕組みの重要性を訴えた。福田氏の起業当初は、こういった仕組みがまだ存在しなかったこともあり、会社をつくるためにはどうしたらいいのか?という一歩目のところで一番苦労したと振り返った。
また2010年に起業した袴田氏も起業そのものよりも、「資金調達がなかなかできないといったところでのハードシングスが多くあった」と語った。
福田氏や袴田氏が語ったのは、仲間や先輩の重要性だった。出雲氏はこういった起業のエコシステムについて「生き物のエコシステムというのは、親子孫の3世代がそろって完成する」と解説した。そのうえで、「IT系であれば、第一世代に孫さん、三木谷さんがいて、第二世代で藤田さん、南場さんがいて、いまも第三、第四世代が生まれている。ディープテックでもこうしたエコシステムを、各大学で作っていかなければならない」と力説した。
出雲氏はまた、多くの起業家が直面する資金調達面のハードシングスについても語った。「資金調達がうまくいかないという起業家の相談に対して、『ベンチャーキャピタル何社訪問した?』と聞くと、だいたい3から5社しか名前が挙がってこない。僕の場合は、『ベンチャーキャピタル年鑑』に載っている会社は全部訪問した。賢い人ってすごく恥ずかしがりなところがあって、3回も断られると、死ぬほど恥ずかしいという。僕の周りで恥ずかしくて死んだ人は一人もいないので。どんなに恥ずかしくても、自分が本当に取り組みたいビジネスであれば、全部いくっていうのが自然にできて、生き残れるのではないかと思う」と自身の経験を交えて語った。
袴田氏も行動力が重要だと述べた。「周りの人が聞いたら驚くようなアクションをいっぱいやって、ここまでするの?と思われていたのではないか。そのくらいやったからこそ、つかめるチャンスがあるのだと思う。ハードシングスは本当にいろいろあって、資金調達周りが一番大きかったと思う。ほかにも、人がどんどん入れ替わっていくような、組織面のチャレンジも多く経験した。そうした経験を経て大事だと思うことは、覚悟というか意思をしっかり持ち続けることなのかな」と語った。月面探査になぞらえて「着陸もそうですけど、1回で諦めてはいけなくて、1回1回の経験を、どう次に生かしていくか。試行錯誤できる体力を残しておくかというのも重要だ」と述べ、失敗から立ち上がるレジリエンスの重要性にも言及した。
袴田氏の話を受けて、粟生氏は「スタートアップはとにかくやってやってやりまくる。失敗しても回復していく力、立ち上がる力が大事」だと強調した。
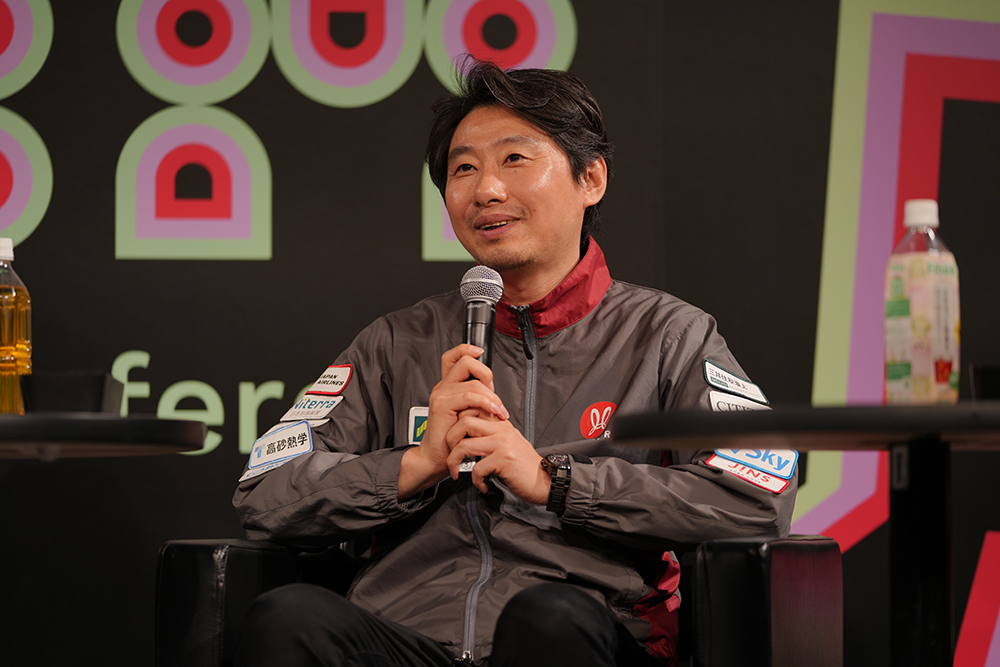
未来に向けてのエール
最後に、粟生氏は登壇者全員に対して、「後輩たちへのエール」を促した。
福田氏は会社を立ち上げることを「発射台」にたとえて、「発射台にのせる前に、ロケット(自身の技術)を完成させていなくてはいけない。一度会社を作ってしまえば、そこからはいつ臨床試験ができるのか?などVCに常に聞かれるような状況になる。会社を作ってからはカウントダウンが始まってしまうので、そこからのんびり研究すればいいやという考えではいけない」と研究者たちを鼓舞した。
袴田氏は「頑固になりすぎてはいけない。研究者だと自分のやりたい道がはっきりしていることが多いと思うが、最終的に到達したいゴールへの道筋は一つだけではない。一つのやり方に固執せずに、諦めずに続けていくということが重要だ」として、柔軟な視野を持つことを促した。
出雲氏は「日本のスタートアップに対するリスクマネーは政府が、5年で10倍にするという約束にコミットしている。小泉内閣のときに大学発ベンチャーを1000社つくるといったときも、それは実現され、いまでは4288社になった。ほかにこんな産業は存在しない。特にディープテックは言語がハンデにならない。世界で優位に立てるという意味でも、ディープテックでスタートアップをする、いまは非常にチャンスのときだ。皆さんといっしょに、5年で10倍という目標に向かって取り組んでいきたいと思う」とまとめた。

粟生氏は「日本の研究技術は世界に負けていないと、自信を持って皆さんに話していただいた。ぜひディープテックのエコシステムを作りながら、皆さんもアントレプレナーとしてこの領域に挑戦していってほしい」と会場全体にエールを送り、セッションを締め括った。
2025年5月7・8日に開催したTECHNIUM Global Conferenceには、2日間で約2000名が参加しました。500件以上の最先端技術・研究シーズのShowcaseがあったほか、医療・創薬・バイオ・クライメートテック、宇宙、AIなど分野別のセッションも数多く開催。そのほかにも、研究者、スタートアップ、投資家、事業会社が集う実践的なネットワーキングの機会も提供しました。商談・マッチングブースでの面談件数は1000件にものぼり、賑わいを見せていました。
TECHNIUM Global Conference
公式Webサイト:https://tcnm-gc.com/